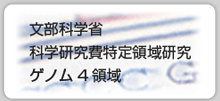パネリスト
| 日髙 敏隆(大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所 所長) | |
|---|---|
1930年東京生まれ。東京大学理学部動物学科、同大学院で、動物学を学び、卒論、博論は昆虫のホルモンの研究。1961年理博。早くから動物の行動に関心を抱き、のち東京農工大学、京都大学などで昆虫やいくつかの哺乳類、魚類などの行動の研究。動物行動学の視点から人間の文化、教育などについても関心をもっている。 講演 :「遺伝的プログラム」なるものをめぐってモンシロチョウの卵は、ちゃんと育つとチョウになる。しかもモンシロチョウという種のチョウになり、けっしてモンキチョウにはならない。その発育の道筋もきまっている。つまり遺伝的にプログラムされているのである。このプログラムを作っているのは、特定の遺伝子ではなくて、遺伝子の集団としてのゲノムである。そしてそのプログラムが具体化されていくのが、生物の発育である。そういう視点から、遺伝子とかゲノムとかいうものを考えてみる必要があるのではないか? |
 |
| 元村 有希子(毎日新聞 科学環境部 記者) | |
|---|---|
1989年、九州大学教育学部心理学専攻卒業、毎日新聞入社。2001年から現職。日本の科学技術を人材育成の視点から検証する連載「理系白書」(2002年〜)取材班キャップ。06年5月、第一回科学ジャーナリスト大賞を受賞。 |
 |
| 宮川 剛(京都大学 大学院医学研究科 先端領域融合医学研究機構 助教授) | |
|---|---|
1993年東京大学文学部心理学科卒業。博士(心理学)。理研BSI・研究員、米国・国立精神衛生研究所・研究員、バンダービルト大学・助教授(研究)、マサチューセッツ工科大学・主任研究員を経て現職。遺伝子・脳・行動の関係について研究を行っている。 |
 |
| 加藤 和人(京都大学 人文科学研究所/大学院生命科学研究科 助教授) | |
|---|---|
1961年京都生まれ。京都大学大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。 |
 |
進行
| 山縣 然太朗(山梨大学 大学院医学工学総合研究部 教授) | |
|---|---|
1958年4月3日、山口県生まれ |
 |
ゲノム談議
| 山縣 然太朗: |  皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、「ゲノム談議」を開始させていただきたいと思います。 私は、今回、司会進行をさせていただきます、山梨大学の山縣といいます。どうぞよろしくお願いいたします。 司会がいるといったような談議ってなかなか変なのですが、今日は、まず、談議ですので、ゲストを紹介する前に、形式から話しますと、ここで、4人のゲストの方、パネリストの方に、とかく自由に話をしていただくのを、皆さんは、むしろのぞき見していただくような感じで、最初は見ていただきながら、そして、1部、2部とあるんですが、1部が終わったときに、皆さんに一度開放して、ご意見をいただいたり、質問をいただいたりというような、そういうふうな形で進めさせていただきたいと思っています。  今回のこの「ゲノム談議」は、皆さんのパンフレットにもありますように、ゲノム研究が進んでいきまして、新しい段階に入り、ヒトについては多数のヒトのゲノムを解析して、ゲノムの多様性と病気のなりやすさの関係を調べる研究なんかが進んでいたり、それから、300種以上の多様な生物のゲノム解読も完了して、医療だけではなくて、ほかの生活・環境など広い分野でその産業応用が進み出しているわけです。そんな中にあって、今回、新鋭のオピニオンリーダーをゲストに迎えて、最前線に立つ研究者も交えて、ゲノム研究の時代的意義、社会的課題について、自由闊達に語り合っていただくということであります。 今回は、人間文化研究機構・総合地球環境学研究所の所長でいらっしゃいます日髙敏隆さん、それから、京都大学大学院医学研究科の宮川剛さん、それから、毎日新聞科学環境部記者の元村有希子さん、そして、今回のこの「ゲノムひろば」の企画・立案・運営をやっていらっしゃいます、京都大学の加藤 和人さんをパネリストに進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 まず第1部といたしまして、日髙さんから、20分ほど、ここにありますように、「遺伝か、環境か」ということで、基本的なお話をしていただきたいと思います。日髙さんですが、先ほど、ご所属はご紹介いたしましたが、もう皆さん、ご著名な先生なので、よくご存じだと思いますが、特に最近、人間は遺伝か、環境か、『遺伝的プログラム論』という本をお出しになりまして、その中の「遺伝的プログラムなるものをめぐって」ということで、最初にお話しをいただくことになります。これが約20分ぐらいです。  次に10分間ほど、宮川剛さんから……。宮川剛さんは、今日、上のパネルでもたくさん発表をしていただいておりますが、心理学の専攻でありまして、心の健康問題について、ゲノム研究で解き明かしているというところで、そのあたりのお話をしていただいて、その後、4人でディスカッションということになります。 後半は、第2部として、もう少し社会的なことということで、「ゲノム研究と社会」ということで、まず元村さんに……。元村さんは、皆さんはもうよくご存じで、社会環境部科学環境部の記者として、いろんなところに執筆、発言をされている方です。第1回科学ジャーナリスト大賞も受賞されており、今回、ここでもう少し社会的なこと、そして、ゲノムの研究者に物申すとか、そういうふうな話をしていただきたいと思っております。 その後、加藤さんから、この研究班の中でも、社会との接点グループというのがあって、そこでのリーダーなわけですが、そのあたりのところをお話ししてもらい、社会の中におけるゲノム研究、それとのかかわりついて談議を進めていきたいと思っております。 では、早速、第1部の「遺伝か、環境か」というところで、総合地球学研究所所長の日髙さんからお話をいただきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。 |
|---|---|
| 日髙 敏隆: | ただ今、ご紹介いただきました日髙でございます。所属は、人間文化研究機構・総合地球環境学研究所というふうに長い名前で、本当は正式には、その前に「大学共同利用機関法人」というのがつくんです。すっごい長い名前になるので、たいていというか、絶対に覚えてもらえませんので、「地球研」という略称にしています。「地球研」は、京都のちょっと北のほうの、元農学部の演習林の中に土地をいただいて、そこに立派な建物ができております。 そこでいろいろ研究をしているわけですが、何をやるかというと、総合地球環境学研究所の名前どおりなんですが、地球環境問題のことをやると、こういう話なんです。地球環境問題というのは何かというと、いわゆるダイオキシンがどうしたとか、どこで毒が出たとか、そういうような環境問題ではなくて、地球温暖化みたいな、非常に全地球的な環境問題、あるいは、砂漠化とか、そういうようなことをやるということなんです。 そういう問題は、実は、地球上にはいろんな動物がいます。例えば、トラとかもいますし、ゾウとか、カバとか、いろんな動物がいるんです。中には、相当凶暴な動物とか荒っぽい動物とかもいるんですが、そういう動物は、実は、地球環境問題というようなことは起こしていないんです。結局、そういう問題を起こすのは、どうも人間だけらしい。なんで人間はそういうことを起こしてしまったかというところから始まって研究を進めるということになりました。そのときに、いろいろ議論をしたんですが、それは、やっぱり人間が自然を支配して生きていこうとする、そういう人間の生き方に基本があるんじゃないか。もとがあるんです。そういう認識に至っております。 例えば、普通の動物だったら、カバなんていうのは、あるいは、ゾウにしても、大量の草を食べますけれども、とにかく地上に生えた草を食べに行って、そこに草がなくなったらよそへ移る。あっちへ行ったり、こっちへ行ったりして、また戻ってきて、こちらへ戻ってとか、そういうことをやっているわけです。 ところが、人間は、自分が食べるものが、まあ米でも何でもいいんですが、そういうものが生えてくるのを待っているわけではなくて、それが足りなくなったら植えてしまえばいいじゃないかというので、農業を始めた。それで、それが人間にとっては大成功だったんです。農業を始めると、食料がいっぱい手に入りますから、人口の枠とか何とかということがなくて済む。どんどん人の数が増えても平気であるということになります。 ところが、そのうちに、人がちょっと増え過ぎてくると、こらイカンわというんで、もうちょっと畑を広げて作物をつくらないと食う分がない。そこで畑を広げるために、木を切って、林を切り倒して、広い畑をつくって、そこに植える。そのうちにまた人が増えてきて、また畑を広げようということになっていくと、どんどんどんどん自然を支配しながら、人間の都合のいいようにしていくんですが、しょせん、それでもって林は減るわ、何は減るわと、いろんな問題が起こってくる。そういうことがもとになって、地球環境問題ということが起こっちゃったんだろうと。 ほかの動物は、いかに荒っぽい動物も、そういうことはしていない。人間だけがそうした。それは明らかに、人間は頭が良かったからできたことなんですけれども、その人間の頭が良かったことがそういうことになった。 それから、もう1つは、宗教的な問題というのが、世界中でいろいろ問題になっています。これも実は、環境問題と絡まった形で宗教の話もあるんですけれども、宗教というのを持っているのは人間だけなんです。人間は、なんで宗教を持つようになったかというと、それは人間は頭が良かったからなんです。頭が良かったから、なんで宗教ができたかというと、これはこういう話です。要するに、ほかの動物は、どうも見たところ、この地球上というか、この世界に、死というものがあるということは知らないらしい。自分の親が死んじゃったときには、何かよくわからないが動かなくなったと。返事もしなくなったと。冷たくなっちゃった。寂しいとは思う。だけれども、これが死というものであって、いずれはそれが自分にもかかってくるということは知らないらしいです。 ところが、人間は頭が良かったものですから、死というものがあることを知ってしまった。これが有名な「死の発見」です。そういうものを発見してしまいますと、これは人間全部、いずれ自分が死ぬということをみんな認識しています。そうすると、死というものに対して、何か自分の覚悟を決めておかないと生きていかれないわけです。そういう不安を持ってしまった。そうすると、結局、そこで宗教が出てくる。すると、その宗教の違いによっては、いろんな問題が起こってくるんです。  そんなふうなことを考えてみますと、じゃ、人間はどうしてそんな動物になっちゃったんだろうと、こう考えるわけです。それで、つらつら考えてみますと、動物といったって、いろんな動物がいます。ゾウなんていうのは、息をするための鼻をこんなに大きくして、長ーくして、それで物を巻き取って食べようとか、場合によったら、それを水にずっと浸けて、水を吸い込んで、それでシャワーを浴びようとか、とんでもないことを考えちゃったんです。ゾウはなんでそんなことを考えたんだろうか。同じように大きいカバさんは、そんなことは絶対にしません。しかし、まったく別のことをしています。あれも動物なんです。どっちも哺乳類です。 ところが、中には昆虫なんていうのがいて、また全然違う生き方をしている。そういう生き方がいろいろとあるんですが、そういうのは何で決まっているんだということになると、これはもう遺伝であるとしか言いようがないではないかと。それで、昔から議論されている、やっぱり人間は遺伝か、環境かというような話になってくると、遺伝も大事だが環境も大事だというお話になります。だいたいそこで話が終わっちゃう。しかし、それじゃ、何だかやっぱりわけがわからないではないか。 中には、遺伝という固定的なものによって人間は決まっていると考えたくない人もいるんです。そういう人は、遺伝ではない、やっぱり環境である、教育であるとか、家庭であるとか、そういうことをいろいろ言い出します。だけど、そういうものなのかなと。やっぱり人間は、赤ん坊が生まれたときには、人間の赤ん坊は、とにかくちゃんと順番を踏んで大きくなっていって、必ず人間になります。子どもが生まれて、だんだん育てているうちに、どうもだんだんおかしくなったと思っていたら、とうとうチンパンジーになっちゃったとか、そういうことは絶対にないわけです。 昨日、九州だったか四国だったか、どこかの新聞社から電話がかかってきたのが、ブラジルでもってネコが、ネコの子を3匹とイヌの子を3匹産んだという話が今非常に有名になっています。それは本当だろうか。そんなことは絶対にないですとぼくは言っています。わけもいろいろ言ったんですが、とにかくそういうことは絶対にない。必ず人間の子どもは人間になる。チンパンジーの子どもは絶対にチンパンジーになるんです。それは決まっているんです。それで、チョウチョの子どもはチョウチョになる。カエルの子どもはカエルになると、皆さん、おっしゃいます。みんな知っているんです。 ところが、本当は、チョウチョの子どもはチョウチョ一般になるんじゃなくて、モンシロチョウの子はモンシロチョウになるんです。ナミアゲハの子どもはナミアゲハになるんです。クロアゲハの子どもはクロアゲハになるんです。そこまで、種としても決まっているんです。カエルだって、カエルの子はカエルになるって、皆さん、簡単に言います。日本でも昔から言われていますけれども、そんな大雑把なものじゃない。例えば、アカガエルの子どもは、アカガエルのオタマジャクシはアカガエルになるんですよ。そして、ヒキガエルのオタマジャクシは必ずヒキガエルになるんで、ヒキガエルのオタマジャクシを飼っていたらば、いつの間にかアカガエルになったとか、そんなことは絶対にない。これはなぜなんだということです。 そのへんの話は、結局、遺伝のことなんです。まさに遺伝的に決まっているとしか言えない。だけど、ここでいう遺伝とは、よく遺伝というと皆さんが思うメンデルの遺伝学の話とはまったく違うことなんです。メンデルの遺伝学はエンドウか何かのある種の植物の花が赤くなるか、白くなるかとかいうようなお話から始まっている。今の話だと、そうじゃなくて、ヒキガエルの子どもが必ずヒキガエルになる。アカガエルにはならへんということなんです。それが決まっている。どうして決まったのか。だれが決めたのか。これはわかりません。 ここの話でいえば、それはゲノムが決めているとしか言いようがないです。遺伝子が決めているという人がいます。しかし、遺伝子1個1個というのは、この本にもちょっと書いてあるでしょう。この地図は、これは配られているんですか。 |
| 日髙: | 上のほうでご覧になったと思いますけれども、まあ人間だって、いろんな遺伝子があります。その遺伝子1個1個が決めているというふうに思うと、どうしても、じゃ、人間の赤ん坊は人間になるということを決める、人間の子は人間になるということを決める、そういう遺伝子はどれなんです? と聞きたい人が必ず出てます。 ところが、そういう遺伝子があるとすれば、チンパンジーの子はチンパンジーになると、チンパンジー遺伝子とかいって、そういう遺伝子があるはずだということになるけれども、そんな遺伝子はどう考えてもあるとは思えない。やっぱり遺伝子の集団が、集団としてやっているんだと。しかも、その集団の中には、このごろわかってきましたが、例えば、人間の遺伝子の集団全体(ゲノム)と、チンパンジーのゲノムとは、何%?90、92……。 |
|---|---|
| 加藤 和人: | (共通なものが)98%ある。 |
| 日髙: | そうすると、あと残りの何%かの中に、人間とチンパンジーを区別する遺伝子があるということになる。そういうことでは、どうもないらしい。じゃ、どうなっているんだと、これは全然わかりません。しかし、そういうものがガチッとあることは間違いないです。絶対に間違いがない。これは環境のせいではないです。どういう環境で育ったって、人間は人間になるんです。個人的にどういう性格の人になるか、それは別ですよ。人間であることは間違いがない。荒っぽいところで育っていると、いつの間にかゴリラになっちゃうとか、そんなことは絶対にない。どこかでばちっと決まっている。これは何なんだ。そこが一番大事なところです。 決まっているというのが1つありますが、決まっているから、じゃ、今度は、放っておいても自然に人間になるのかといえば、そんなことはないです。これは、もう親が一生懸命お乳をやったり、食べ物を食べさせたり、病気になったら死なないように治すとか、いろんなことをして、手間暇をかけてやっていかなければ育ってはいかない。育っていったら人間になるわけです。必ず人間になる。 チンパンジーと一緒に育てていても、必ず人間は人間になる。上のところにさっきありましたが、「牛肉を食べていても、なぜウシにならないんですか」というのがありました。あれも、一応人間の遺伝子がガチッと決めているわけです。 そういうことを言えば、これは僕も昔、不思議だったのですが、同じ原っぱの同じ草を食って、ウシとウマがいるわけです。そして、ウシとウマがいて、絶対に、同じところを食っているから、だんだん両方が似てきて、ウシともウマともつかないようなものが増えちゃうことはないんです。同じものを食っていても、ウシはウシでウマはウマなんです。片方には角がちゃんと生えていますし、ウマにはどうやったって角が生えてこないんです。それも決まっている。 そのへんのことがやっぱり遺伝子の集団がやっていることだから、この遺伝子の集団というのをゲノムというふうに考えていいんだと思うんです。そうすると、このゲノムの研究というのは、今言ったような、根本的な問題を研究していることになる。ただ、これは非常に難しい問題でしょうから、簡単にわかるとは思えません。しかし、たぶん、上でいろんな人が研究しているし、ここでもそういう方がいっぱいいらっしゃるわけですけれども、やっぱりそれを知りたくてやっているんだろう。基本的にはそういうことです。そういうことをやっていけば、それが病気を治すとか、病気を止めるとか、何かそういうことにも使えることは使えるでしょう。あるいは、新しい品種をつくるとかいうことにも使えるでしょう。でも、それは、そういう応用的な話なのであって、基本的にいうとそういうことです。ゲノムが加わると、そのゲノムがなんで人間……、つくるというと変ですね、なるのかということです。そのときには、ちゃんと物を食べている。 例えば、モンシロチョウなんかの場合には、何を食うかということも遺伝的にぱちっと決まっています。アブラナ科植物の葉っぱを食うということは決まっています。そして、アブラナ科植物には、カラシのような匂いのするカラシ油という物質があって、カラシ油の物質が必ず入っている。これがびりびり入っているのがカラシの葉っぱで、カラシの種なんていうのはすごく辛くなります。大根だって辛いときがありますね。ちょっと油が入っているんです。それはアブラナ科植物の特徴です。これもまたゲノムの問題でしょうけれども、とにかくそうなっているんです。 そうすると、これは単なる菜っ葉じゃないんです。栄養的には、アブラナ科植物でなくても、例えば、レタスを食わせたって、栄養的には絶対にいいはずなんだけれども、モンシロチョウの幼虫はレタスの葉っぱをやっても、あるいは、ホウレン草の葉っぱをやっても絶対に食おうとしません。それは遺伝的に決まっちゃっているからです。匂いをかいで、カラシの匂いがしないと、これはだめ。もう食わない。どんなに腹が減っても食わないんです。で、飢え死にします。そういうふうになると、本当はモンシロチョウになるはずだった遺伝的プログラムがあったんだが、そのプログラムは現実にはならなかったということです。 そうすると、結局、そのプログラムというのがあって、現実になるというのは、どういうことなんだというのを、ちゃんとすべて行かないといけない。元のプログラムというのは何なんだということもわからなきゃいけない。そういうことを研究していくのは、このゲノムの研究なんだろうと僕は思っています。  今すぐ、ゲノムはわかった……、一時、ありましたね。ヒトゲノムがわかったものだから、それから、ヒトゲノムがわかられて、人間はみんなわかりますというんです。将来はみんなわかるというんです。その将来がわかるか、わからんかという話は昔からあったんですが、子どもの本に書いてありました。たいていの子どもたちは、自分たちの未来が、将来がどうなっていくかわからない。つまらないと。先がわかったらいいのになと、みんな思っている。しかし、とんでもない。先がみんなわかったら、つまらなくて、生きている気がしなくなるでしょう。それはそうなんです。先がわからんから生きているわけです。 そういうふうなことになると、やっぱりゲノムの持っている遺伝的なプログラムを具体化していく。これはアクチュアリゼーション(actualization)と言っていますが、現実のものにしていくということが問題です。そのへんのことを、やっぱりちゃんと研究していく必要があるだろうなと思うわけです。そのために、ここではいろんな研究をされているんだろうと思っております。一応、今日は、こんなところです。 |
| 山縣: | どうもありがとうございます。遺伝的プログラムということがどういうふうなことなのかということを、少しご理解いただけたかと思いますが、この後、またこれについて、4人プラス・アルファーで議論を進めたいと思います。 次に、宮川さんからお話をいただきます。宮川さんは、先ほどお話ししましたように、京都大学で心の健康といいますか、例えば、統合失調症の研究だとか、そういったものを、マウス……、上でパネルをご覧になった方がいらっしゃると思いますが、ある遺伝子を働かなくして、そして、その違いはどういうところになるのかということを調べることによって、その遺伝子の働きなどを明らかにするといったようなところの研究を中心にされているわけです。そのあたりも含めて、宮川さんからお話をいただきたいと思います。では、お願いします。 |
| 宮川 剛: | どうもありがとうございます。京大の宮川です。今、日髙さんから、遺伝的プログラムというのが種によって決まるといって、ヒトはヒト、ゾウはゾウ、虫は虫というふうになるというお話があったんですけれども、私からちょっとお話ししたいのは、遺伝的プログラムというのが種ごとにある。けれども、その中で、その種の中でも、同じ遺伝的プログラムであってもかなり変わってくる可能性があるし、それから、遺伝的プログラムにいくらかの差がある。それも無視できないような差があるというお話をちょっとしたいと思います。 まず、遺伝的プログラムが環境の違いによって変わってしまうのかということなんです。これはラットなんですけれども、齧歯類のラットです。そのラットが、母親がいます。子どもがいます。この子どもをたくさんなめたり毛づくろいして育てるラットと、そうでもないラットがいるんです。これは遺伝的にまったく同じでも、そういう親のラットと、そうでないラットがいるんです。  最近のゲノム科学では、これはいったいどういうメカニズムによってできているのかというのが、だいぶわかってくる。それはどういうことかというと、この場合、たくさんなめたり毛づくろいをしますと、子どもの脳のゲノムの上で、グルココルチコイド受容体というある遺伝子があるんですが、その遺伝子のディメチレーションということ。ゲノムがこういっぱいあるわけですが、そのうちの遺伝子が発現したり、発現しなかったりするのは、そのメチレーションとか、アセチレーションとかいう、エピジェネティクス(epigenetics)といわれているんですけれども、そういうものに制御されているといわれているんですが、そういうものはかなり長い時間効くということがわかっています。たくさん世話をすると、そのメチレーションが外れて、これがたくさん出るようになる。その発現増加が大人になっても持続していく。そうすると、不安が少なくて、ストレスに強くて、自分も世話をする親になるということなんです。 これは、ゲノムの違いじゃなくて、環境の違いによってこういうのが起こるという話です。面白いのは、これは生後1週間だけで効果があります。その時期を逃して、その後でこういうことをやっても効かないということがある。これが1つです。つまり、遺伝的プログラムというのは、適切な時期に、適切な刺激で具体化される必要があるというのは、最先端のゲノム科学で具体的に明らかになるということなんです。 それから、次に、遺伝的プログラムに個人差がある。種内での差はあるということなんですが、心や行動の性質も、遺伝子の違いによって影響を受けるのだということなんです。これは、一卵性双生児と二卵性双生児を比べることによりまして、こういった一般的知能とか、愛好性とか、病気とか、そういったものが遺伝するということは、かなり前からわかっていました。何十年か前から、こういうものはかなりの率で遺伝するということはわかっていました。それから、精神疾患のようなものも遺伝するということもわかっていました。しかしながら、具体的にどういうタンパクが行動する、どの遺伝子がどのような行動や心の特性に影響を与えるかというのを調べる方法はありませんでした。 しかしながら、これは15年ぐらい前なんですけれども、遺伝子ターゲッティングという方法が開発されました。これはマウスで使えるんですけれども、マウスで、特定のねらった遺伝子、ある特定の、例えばカルシニューリンとかいう名前の遺伝子があるんですけれども、そういうねらった遺伝子を自由自在に改変することができる。なくしちゃったりすることができる。そういうことができるように、これはごく最近なりました。 この方法は、ちょっと説明は省きますが、とにかく、ある遺伝子を持っているマウス、持っていないマウスをつくることができる。同じ親から10匹ぐらいマウスは生まれますけれども、その中で、その遺伝子を持っているマウスと、持っていないマウスと、兄弟で用意することができます。 そうしまして、行動の違うもの、こっちのマウスが何か行動な異常を示せば、その遺伝子Xがその行動に影響を与えているということになる。どうやって行動の性質とか心の性質を調べるのかといいますと、こういったテスト、痛覚のテストですけれども、こういうテストとか、それから、運動機能のテストとか、活動力、それから、不安様行動、どれだけ怖がりかと、そういうものとか、それから、こっち、一種の注意力のテストです。それから、これは学習記憶の能力のテストですが、そういうものをテストすることができます。 これは、皆様、ご存じだと思いますけれども、日本で1人だけノーベル医学・生理学賞を取った人がいまして、それはこの利根川先生なんです。利根川先生は免疫の研究でノーベル賞を取られたんですが、取った後に、免疫の研究はちょっともう自分としては興味がなくなってきた。脳とか心の研究のほうが面白いということで、分野を変えられまして、この遺伝子ターゲッティングの方法を心の研究に初めて使いました。これは世界で初めて使いました。それ以来、これは爆発的に使われるようになったんですが、私はその利根川先生のところへ行って、研究をしばらくしていたんです。 その中で、いろんな遺伝子をノックアウトした、なくしたマウスができているんですが、すごく面白いマウスがこのカルシニューリン欠損マウスというものでありまして、このマウスというのはいろいろな異常を示します。作業記憶の異常とか、社会的行動の異常とか、それから、面白いところでは、アルコールがとっても好きになります。お酒がとっても好き。それから、このマウスはニコチンがとても好きなんです。ニコチンが入った水をいっぱい飲むんです。 とってもすごいマウスなんですが、これは、こういういろいろな異常があるんですけれども、この異常のパターンというのが、実は、ヒトでいえば、統合失調症という疾患の患者さんの行動異常のパターンと非常によく似ているということがあります。統合失調症というのはどういうものかといいますと、全人口の1%、100人いれば1人いるということです。幻覚や妄想とか、極度の興奮などの症状がありますし、社会的引きこもりなどの症状があります。それから、こういった認知機能の障害。 それから、どうやって疾患になるかというと、遺伝的要因と、それから、ストレス、引っ越しなどのライフ・イベントという原因において環境要因によって発症する。こういうゴッホとか、ムンク、ジョン・ナッシュ、夏目漱石なども患者であったといわれています。しかしながら、発症のメカニズムがどういうものかとか、発症に影響を与える遺伝子がどういったものがあるかというのは、よくわからなかったんです。 その研究からけっこうわかってきたということなんですが、マウスの研究でヒトのことがわかるのかということが、そこで疑問が1つできたわけです。これは赤ちゃんなんですけれども、kitという名前の遺伝子を欠損した子どもなんです。ほとんど正常なんですけれども、額のところにこういう白く色素が出てくる。これはヒトです。マウスでkitという遺伝子をなくした、先ほどの遺伝子ターゲッティングでなくしたマウスは、どうなるかというと、やはり同じところにこういうのがあります。 つまり、けっこうヒトの遺伝子とマウスの遺伝子は共通していまして、マウスの遺伝子の99%は、実はヒトでホモロを持っている。ホモロというのは似た遺伝子なんですけれども、それを持っていると。つまり、心の研究でもマウスは使えるだろうということがありまして、そういうことから、ヒトでも、さっきのカルシニューリンがどうかということを、患者さんとそうじゃない人のDNAをたくさん集めてきて調べています。そうしたら、カルシニューリンの遺伝子のある多型のパターンと、それから、統合失調症になりやすいかどうかという危険性に相関があるということを、われわれは見つけました。さらに、統合失調症の患者さんの死後脳では、先ほどのカルシニューリンの遺伝子が落ちているということも見つけました。 これはまた別のマウスです。Camk2という名前のついたマウスなんですけれども、このマウスはすごいんです。どういうことかというと、このマウスは同じケージに入っているんです。兄弟は、次々と殺します。普通は殺しません。4匹ぐらい入れまして、2匹、ミュータントで入れていくんですけれども、仲良くしています。しかしながら、このマウスというのは、普段仲良くしていますが、突然、次の日に見ると1匹死んでいる。普段仲良くしているんですけれども、おそらくケージの中で何かちょっとした気に食わないことが起きているんでしょうね。そこで、キレてしまう。殺してしまう。6カ月ぐらい経つと、1匹のミュータントのマウスだけ残る。つまり、ある1つの遺伝子の発現が半分減っただけで、兄弟を殺すプログラムが機動されてしまうということが起こり得るということなんです。 われわれの研究室、京大の研究室では、たくさんの遺伝子改変マウス、これは、1つ1つの列が、1つの遺伝子が失われたものですけれども、例えば、この列のマウスですと、不安様行動が上がっている。怖がりになる。ある遺伝子を壊すと怖がりになる。それから、このマウスでは活動量が高くなって社会性が上がっているということです。この図を見てわかることは何かといいますと、これは全部1つ1つ違う遺伝子のノックアウトマウスですけれども、どういうことがわかるかというと、すべての遺伝子の半分以上は脳で発現しているんです。これは50個、だいたいかなりランダムに取ってきているわけですが、1つ1つの遺伝子が、皆それぞれ行動の心の特性に何らかの影響を与えていることがある。ほんどの場合、影響を与える。つまり、すべての遺伝子の半分以上は、脳で発現しているんだけど、そのうちの多くは、心の特性に影響を与えているということなんです。脳の神経系で発現している遺伝子の多くは、何らかの影響を。 ヒトのゲノムというのは、30億塩基対あるんですけれども、最低でも1,000塩基対に1つはスニップ(SNP)、Single Nucleotide Polymorphismといいまして、これが存在する。スニップというのは、その1つのところで、1人1人多型が存在するんです。私はA型、あなたはC型と、そういうのが存在するわけです。これは何かといいますと、これはチップなんですけれども、実物はもっと小っちゃいんですが、これに65万個の小さいスポット。1つ1つのスポット、小さい点がいっぱいあるわけです。1つ1つのスポットで、ある人の遺伝子、ゲノム上のスニップが、A型なのかC型なのか、わかってしまう。それが、25万個がこのチップ1枚でわかってしまう。血を採ってきて、DNAを採って、それをちょっと加工してこれにかけると、65万個のものが一気にわかってしまうということなんです。 つまり、このようなチップ1枚で、もしかすると、将来的に、これは今そうはなっていないですが、ある人がどのような疾患にかかりやすいか、どのような性格の人か、予測できるような時代が来るかもしれない。先ほど、日髙さんから、将来が予測できてしまったら面白くないというお話があったんですが、そういう面白くない時代になってしまうかもしれない。 ただ、1つ1つの遺伝子がどういう意味を持っているのかわかりませんので、まだそういう状態にはなっていないということなんですが、1つ言えることがあると思うんです。そういうことがあるんですが、遺伝的プログラムには個人差があるので、そのプログラムを具体化していく。教育とかそういうものでそうしていく際には、個人差も考慮する必要があるだろうということが言えるだろうと思います。以上です。 |
| 山縣: | 地図はありますか? 全員ではない?! |
| 山縣: | はい、どうもありがとうございます。今、宮川さんからは、日髙さんが最初お話しになった、遺伝的プログラムというのが、もう既に、例えば、先ほどのマウスの研究なんかで、遺伝子のレベルでも少し明らかになっているところはあるんだというところと、あと、もう1つ、一方で、種の中にも個人差があるので、それを遺伝的プログラムとしてどういうふうに考えていかなければいけないのかという、そういう話だったというふうに思います。 ここからは、4人を中心に、今のあたりのところで議論していただきたいと思います。その前に、先ほど、少し日髙さんから、上でヒトの遺伝子のことが何かこうわかったね、ということがあったわけです。 ここにポスターがありますが、ゲノム・マップというのが上にあるんですが、それを見ていただくとわかるかなという気がします。それで、配布物もありました。ゲノム・マップは、皆さんに配布するのは少しまだ余ったのが……。 |
|---|---|
| 加藤: | お帰りのときに、全員の方に差し上げます。 |
| 山縣: |  ということですので、こういうふうなマップが、遺伝子の多くはできているのというのを見ていただければと思います。それから、チンパンジーとヒトの遺伝子の違いってどれぐらいあるのかというのも、最初、これは、藤山先生がいらしたらお話しいただくと一番いいと思うんですが。最初は、何か、1.数%ぐらいだったんだけど、もうちょっと別の見方をすると、もう少し何か違いがあって、違う部分にホットスポットがあるような、そういう話を伺ったような気がするんですが、そこだけちょっと何か……。 |
| 加藤: | いきなりフロアに。 |
| 藤山: |  すみません、藤山でございます。何か突然、ちょっと予想外のあれですけど。基本的には、日髙先生がおっしゃられたとおりでして、どこか特定のところに変化が起きているんだろうということは、まだ見つかっていないんです。ただ、ある時期にいろいろな場所で、集中的にいろんな変化が起きたんだろうなという形跡は見つけています。それは、ヒトの側にも起きていますし、逆にチンパンジーの側にも起きています。そういう経過、そういう痕跡だけはゲノムで見つけましたが、じゃ、それぞれが何をやっているかというのは、まだ依然として、これからの段階です。すみません、簡単で。 |
| 山縣: | はい、ありがとうございます。少し、途中で、私も答えられなかったところがあったので、ちょっと説明いただきました。 じゃ、4人の方にお話を進めていただいて、皆さんは、そこを、最初はのぞいていただくということにしたいと思います。はい、どうぞ、もう手を挙げずにやりましょう。4人でどうぞ。 |
| 加藤: | はい。本来は裏方のはずの加藤でございます。やっぱりちょっとは出ろということなので、出てきています。 お二人の話、今、短いお話をそれぞれいただいたので、私としては、もう少し、日ごろ話をしているというか、事前に話をしたところあたりから、ちょっと補足的な質問を兼ねてお聞きしておきたいなということがあります。2点、お聞きしたいです。 1つは、たぶん今、宮川さんは、かなりこんなことがわかるよ、とおっしゃったと思うんですが、特に最後のチップのあたりは、将来ここまでわかるかもしれないとおっしゃったのですが、本当のところはどうなんですか。というのは、僕はいろんな研究者とやっていてると、苦しんでいる人はいっぱいいるので、わかろうと思ってもわからないケースがあるというのが1点。 それから、もう1つは、日髙先生が遺伝的プログラムということをおっしゃって、種は、それぞれの種はそれぞれの種だよという話をおっしゃったんですが、その種のプログラムが働くためには、やはり環境が必要で、そういうことに、先生は、最近、青少年科学センターというところで、子どもさんの教育とかにもかかわっておられます。要するに、プログラムを発現させるためには、さまざまな環境が必要だと思うので、そのへんの話を少し、お二人にお話していただきたいんです。 |
| 宮川: | チップでわかるようになるかどうかと。本当のところはどうかと。これは、本当のところはどうかというのは、僕にも本当のところはわからないんですが……。 |
| 加藤: | さっきはものすごく自信ありそうにしゃべりはったんですけど。聞いている人は、みんな、ちょっとびびったんじゃないかと思うんです。 |
| 宮川: | しかし、これに関する知識は、今後どんどん研究されて、どんどん蓄積されてくるのは間違いないです。例えば、アイスランドという国がありますが、そこでは、すべてのヒトからDNAを採って、その健康状態もチェックしていて、精神疾患にかかわったとか、そうじゃないとか、そういうデータも取っています。そういう、すべての人からそういう情報を取って、あのチップを、65番スニップのチップをやります。そうすると、このスポットでこのタイプの人は胃ガンになりやすいとか、このスポットでこういうタイプの人は、アルツハイマー病に何歳になったらなるとか、そういうのがわかってくるようになるんではないかなと。精神疾患……。 |
| 加藤: | だいぶ長いことやってはるんですか。アイスランドはだいぶ長いことやっていますけど、いくつか出てきているのは本当です。 |
| 宮川: | 65番スニップは最近できたから、そのうちわかってくるんじゃないですか。 |
| 加藤: | ありがとうございます。もうちょっと言いたいことがあって。 |
| 山縣: | 環境の話に移っています。どちらでも、日髙先生。 |
| 日髙: | どうもそのへんで、何となくよくわからないのは、プログラムが……。 |
| 山縣: | プログラムがあるということはいいんですけれども、プログラムが働くためにはさまざまな条件が必要で、例えば、モンシロチョウの幼虫はちゃんと葉っぱを食べないと餓死しますし、人間だったら、やっぱり教育がないと賢くならない部分もあると思うんですが。 |
| 日髙: | 要するに、そういうことなんです。僕は、それをプログラムの具体化と呼んでいるんです。具体化というと変な言い方なんですが、具体化というのは、僕が使い始めた言葉なんです。要するに、プログラムというのは、そもそも何だということなんです。プログラムというのは、要するに、筋書きが決まっているということだと、僕は理解しているんです。 ここにはありませんけれども、学校の入学式なんていうのがもしあると、入学式のときに、だいたい「式次第」という紙があって下っています。最初に「開式の辞」というのがあって、それから、「校長あいさつ」とか、「来賓祝辞」とか、いろいろ書いてありますね。それがプログラムです。このプログラムは、そこの式場に来た人たちが、そこで相談をして決めたことではない。何か、いつの間にか決まっているんです。それは、式が始まるより前に決まっているんです。という意味において、ある意味では、遺伝的に決まっているというのと同じような感じがする。その1個1個はそういうことが書いてあるんです。 例えば、「開式の辞、事務局長」と書いてある。そうすると、こういうところに演壇があるんだけれども、事務局長さんは、わざわざ向こうから出てきて、てくてくとずーっと歩いてきて、今度はここへ来て、そこでもって皆さんに丁重にお辞儀をして、それから、やおら「これから何とか学校の入学式を始めます」と言います。それだけ言って、深くお辞儀をして、また元のところへ帰ります。くだらんといったら、これほどくだらんことはないんですよ。だけど、それをやらないと、プログラムの一番上のプログラムが具体化されないんです。 その次に、今度は「校長あいさつ」。「校長あいさつ」というのは、校長があいさつをするということが書いてあるだけなので、どういうふうにするかわかりません。校長先生といったっていろいろな人がいますから、ひょこひょこ出てくる人もいるかもしれないし、堂々とというか、変な、落ち着き払ってというか、もっともったいぶってとか、いろんな言い方があるんですけれども、出てくるでしょう。そこでもって、いきなりしゃべり出す人もいるかもわからないが、ポケットから何か出して、こういうのをこうやって、こうやってもいいですし、広げてこうやって読み始める、そういうのもいるでしょう。中には、言われたことはほとんど意味がないほどつまらんことであるとかいうこともある。しかし、それが終わると、つまらなくてもつまっても、皆さん、やっぱり一応拍手しますね。そうすると、そこでお辞儀をして、また戻ります。それで、2番目のプログラムが具体化されたことになる。 だから、この中には、校長があいさつをするということがプログラムとして決まっているだけで、何を、どう、どんなことを言うかとかということは、一切触れられていない。しかし、校長はとにかく出てきて、何か言わなきゃいかんのです。そうしないとだめなんです。 |
| 加藤: | だから、そこで校長の話が長かったり面白くないと、生徒たちはこんなになって。 |
| 日髙: | そうなんです。それはまあ。 |
| 加藤: | 面白かったら、まあある程度、まだ式だというとちゃんとしているかもしれないですし、いろいろ変わるわけですね。 |
| 日髙: | それはそうです。だから、そのときに、そういう順番で具体化をされなければいけないと、こういうふうになります。いろいろあります。 例えば、どういうときもよくあるんですが、「来賓祝辞」というのがあるとすると、だいたい学校関係、特に大学関係ですと、必ずあの「文部大臣の祝辞」というのが入っています。文部大臣はまず絶対に来ませんから、必ず代読ですよ。その代読の人が出てきて、それも必ず預かったものを読んでいくんですが、それは紙に書いたやつを広げてこうやって読む。だいたいそういうのは決まりきっていますが、「桜咲くこの4月……」というようなくだらん話です。でも、そういうのがないとやっぱりだめなんです。終わらない。それが具体化なんです。 具体化のされ方というのは、いろいろあります。でも、とにかく具体化はされなきゃいけない。だけど、その前にプログラムがないと、次の式辞のときにだれが出てくるかわからない。突然にだれかがぽっと出てきて、ばっとあいさつが始められたら困るんです。それは困る。やっぱりプログラムがきちっと決まってないと。そういうふうなことがあるということが、まず大事な話です。  2つが今日の問題だと。それで、具体化されるときに、どう具体化されるかというときに、やっぱり条件がいろいろあるし、され方もいろいろある。それによって反応も変わるわけです。その式が、プログラムとして書いてある式が、とっても意味のあるいい式だったということになるかもしれないし、くだらん式だったなというふうになることもあるわけです。そのへんで全部のことが決まってしまうんで、やっぱりそこで元のプログラムが絶対に必要であると同時に、具体化されることが必要で、かつ、そのされ方が問題であるということについては、あらゆる場合において同じなんじゃないかと。 |
| 加藤: | さっきチンパンジーが出ましたけど、チンパンジーじゃなくて同じ霊長類のオランウータンというのがいますよね。オランウータンは森の賢人ですけれども、あんまりたくさん一度に同じところに住んでいないと思うんです。それに比べて、人間というのは、気がついたらこうやって集まっているわけです。こんなところにいっぱい集まっているじゃないですか。そういうことも何か大事なんじゃないかというのをおっしゃったような気がするんですけど。 |
| 日髙: | 人間、そうです、オランウータンというのは、1匹1匹で別々ということになっていましたが、このごろの話では、必ずしもそうではないんです。 |
| 加藤: | そうですか。いい加減なことですみません。 |
| 日髙: | かなり、1匹のオスが何匹かのメスのところをぐるぐる回って歩いているそうです。やっぱりほかのオスは、そのオスになりたいんで、オス同士のけんかは相当にあるという話でした。 とにかく、いずれにしてもそういうふうになっているんですけれども、人間の場合には、これだけ人が集まっても大丈夫なんです。チンパンジーがこれだけ、何匹ですかね、300匹ぐらい、チンパンジーの場合、集まったら、もうチンパンジーは絶対にこう静かに座っていてくれませんよ。これも人間だから、ちゃんと座っているわけです。そういう意味では、やっぱりその動物にとってのある行動パターンみたいなものが決まっている。1つずつに。今、宮川さんが言われたみたいに、いろいろ異常があるし、違いはあるんですが。さっきのお話もいろいろありまして、面白かったんだけれども、逆に言うと、変なふうな言い方をすれば、しょせんマウスだからでしょう。マウスがああやっているうちに、何かほかの動物になっちゃうわけではないんです。マウスは絶対にマウスなんです。 これは、前にも僕は突然変異の話、ミューテーション(mutation)の話を聞いたときに思ったのですが、キイロショウジョウバエという種類があります。これは、ショウジョウバエというのはいっぱい種類があるんだけれども、その中でも一番よく飼われているのがキイロショウジョウバエという、ドロソフィラ・メラノガスター(Drosophila melanogaster)とか何とかっていう学名のついたそういう種です。それの突然変異はいろいろのものが、羽がなくなったり、4枚生えてみたりとか、いろんなのがあるのですが、とにかくキイロショウジョウバエの突然変異であることは間違いなくて、突然変異をやっているうちに、それが別の種であるクロショウジョウバエになっちゃうとかいうことはないんです。絶対にないんです。 遺伝的プログラムの不思議さというのはそこにあるんで、なぜそこを越えないんだろうと。中ではいろいろ違いはあるんですが、キイロショウジョウバエという種であるということは間違いない。これは、だれが、どうやって決めているんだということです。これは非常に問題なんです。そこまでゲノムの話が行ってわかると、われわれは非常にいろいろなことがわかるわけです。だけれども、そうじゃないと、どうもそれがわからないままになる。 |
| 山縣: | そこが難しいところですね。 |
|---|---|
| 日髙: | そうなんです。 |
| 山縣: | 元村さんが何か、先ほどありましたが。 |
| 元村 有希子: | さっきの兄弟殺しをするマウスの話がありましたね。宮川さんの論理で行けば、マウスとヒトとは99%ゲノムが一致しているので、人間にもCamk2が欠損していたら、兄弟殺しをするということになって、それはあらかじめ調べて殺人を予防できるということになるんですか。 |
| 宮川: | なるかもしれないですね。われわれはヒトの遺伝子も実は調べているんですが、そういうヒトのサンプルというのがなかなか取得できない。よく言われるのは、刑務所とかに行ってDNAをもらってきたらいかがですかと言われるんですが、なかなか倫理的な問題とかそういうことで、実際には無理なんです。そういうことをやってみたら、中にはいるんではないかと。 |
| 元村: | そう疑っているから、今、マウスで一生懸命研究をしているんですよね。 |
| 宮川: | そうですね。 |
| 元村: | もう1つ気になったのは、子どもの世話をするラットの話。同じゲノムなんだけれども、環境によって子どもにそれが遺伝して。 |
| 宮川: | そういうことですね。 |
| 元村: | 子どもも、自分の子どもの面倒をよく見るようになる。私は聞いていて、児童虐待のことを思い出したんだけれども、児童虐待やネグレクトをする親は、小さいころ虐待された経験がある人が多いと言いますよね。そういうことと関係づけて考えたりしているんですか。 |
| 宮川: | そういうことだと思います。先ほどご紹介した研究の論文は、非常に社会インパクトも大きくて、よく取り上げられているんですけれども、そういうこととまさに関係しているんではないかと。それで、面白いことに、先ほどのは2004年の論文なんですが、同じグループから、最近、また論文が出ているんですけれども、そういうことというのは、大人になってから、メチレーションとかを変える薬を投与することによって変えることができる。 |
| 元村: | それはネズミの話ですか。 |
| 宮川: | ネズミの話。まだヒトでは調べていないんですが、それを変えることができるということ自体が、かなりそれは重要なことで、それは子どものころ、1週間の間にそういう世話をされなかったら、もう一生そういうことなんだというふうになってくると、これは、自分はそういう虐待して育てられたからもう絶望的なのかと。親になってもそういうふうに……。 |
| 元村: | そこなんですよね。人生は変えられないのかということになりますよね。 |
| 宮川: | 運命づけられちゃって、変えられないのかということになってしまうわけで、それは薬で変えられるかもしれないし、薬じゃなくても、おそらく何か訓練をしたり、そういうことによってそれが外れたりするかもしれないわけです。 |
| 加藤: | 談議なので、僕はついややこしい方向に話を持っていくんですが、ちょっと今のは気をつけないと、現実の虐待が、全部そういうふうに、もともと決まって起こっているかの話になっているけれども、実は2つのことが重なっています。ひとつは、日髙先生の最初のプログラムがちゃんと具体化するという話と重なっていて、ちゃんと具体化すればちゃんと行くところが、ちゃんと具体化していないからいろいろ問題が起こっているという話で、もうひとつは、遺伝的プログラムの個人差で、もともとできなくなっているから、要するに、いくらきれいに具体化しても具体化できないわけです。その話がごっちゃになっていて、これはものすごく気をつけないといけない。 というのは、僕が今言った2つのことの、前者のほうが僕はやっぱり多いのではないかと思うので、前者のことを後者に結びつける話になる。今日の話はかなりそういうところがあって、今日はそこの見極める議論をしたいんですけれどもね。 |
| 山縣: | どうですか、今の話。前者のところというのは、環境の……。 |
| 加藤: | 個人差は、そういうふうになっていないのに、わかります? |
| 宮川: | そういうふうになっていない? |
| 加藤: | 虐待するような遺伝的個人差があるわけではないのに、プログラムの具現、具体化がうまくいっていないので虐待してしまうという、別の理由ですよね。 |
| 宮川: | そういう理由が、かなり実際にはあるのではないかと。これは遺伝的な問題ではなくて、そういうふうな環境でされたからそうなっちゃうという場合がある。 |
| 加藤: | 遺伝的な環境だね。 |
| 日髙: | そのへんはやっぱり大事なところだと思うんですが、例えば、まさに環境的にそうだったからという場合があると同時に、今、宮川さんが話されたみたいに、本当に遺伝子的に、遺伝子としてそういう遺伝子が欠けているとか何とかということも実際にあり得るわけでしょう。ただ、あり得たときに、調べたらわかるとして、この人は遺伝子が欠けているから、これは将来人を殺すと。じゃ、その前に殺しておこうかということにもなりかねないですよ。 |
| 元村: | そうそうそう。あとは、生まないとか、隔離するとか。 |
| 宮川: | そうですね。だから、生まないというのもできる。 |
| 日髙: | そのへんのことがあるんです。だけれども、さっきの入学式の話で言ったように、一応式のプログラムは決まっている。大筋は決まっている。そこでもってうまくやると、とてもいい式になる。あるいは、校長先生のお話はとてもいいお話でしたというのと、くだらん話だったというのと、いろいろできてくるわけです。そのへんの話というのは、べつに遺伝子の問題じゃないわけです。それは、話の下手な校長、遺伝子的に……。 |
| 加藤: |  問題は、どういう環境が、例えば、今言ったようなことが起こらないようにさせるのか。つまり、さっきから何遍も言いますけれども、プログラムがちゃんと具体化するのかということが、結局、プログラムの実態がわかっていないので、われわれは今まで知らないわけです。いろんなことを推測して言っているんだけど、そこをこれから見極めて、そっちをまずやってほしいわけです。そう思いませんか。 |
| 元村: | 何か断片的に、1対1の遺伝子を見つけることよりも、全体のプログラムを描いてほしいかなというのはあるんですよね。 |
| 宮川: | 全体のプログラム。1つ思うのは、具体的にその遺伝子を突き止めるという話と、そうじゃなくて、べつに遺伝子も何もわからない。それはどうでもいいんだけれども、攻撃性が高そうな人を、どういうふうな環境にしておけばそういうことが起こらないのかというのは、それは遺伝子の話とまた独立……。こういう育て方をすると攻撃性が増す、こういう育て方をすると、一般的に遺伝子がどうであろうが、攻撃性が減っていくと。そういうことってあると思うんですけれども。 |
| 加藤: | 今日の日髙先生の話とつなげると、それは、要するに、遺伝的プログラムの具体化という話なんです。人間が人間になるんで、育てるときに、人間が必要以上に攻撃的にならない環境があるわけです。 |
| 日髙: | だから、そのへんのことは、結局、人間の場合にはまたいろいろあるんです。1つは、今、育つ途中で、これは発達心理学の問題みたいな気もするんですが、そのときに、人間という動物はというふうに、僕はいつも考えるんです。僕は動物学科なんていうところを卒業しちゃったものだから、ついついそういうことになるのかもしれませんけれども、とにかく人間という動物はどういう動物なんだとずっと考える。 人間の親が子どもを育てます。だいたいは、家族の中で、家庭の中で子どもを育てます。ところが、ネコなんていう動物は、あれは、メスネコがオスネコと繁殖期にうまく出会って、何かちょちょっと、難しいことがいろいろあるけれども、うまくいって、するべきことをしたとしますと、それが済んだらば、もうメスネコはオスネコを追っ払っちゃうわけです。そういうふうにプログラムされているんです。そのときに、そのオスネコが悪いとか、女に対して気が配れないとか、そんなものじゃなくて、メスネコはオスネコを追っ払っちゃうんです。追っ払ってしまって、オスネコもそのまま遠くに、どこかに行っちゃうんです。 人間の場合だったら、そういうことがあったら、必ずどちらか、たぶん女のほうからでしょうけれども、ちゃんと保険をかけておきましょうね、なんていう話が出てくるわけですが、ネコはそんなことを絶対に考えません。そのメスネコは1人で妊娠して、子どもを産んで、母親が1人で子どもを育てます。 そうすると、そこでいろんな問題が出てくるんですが、今度は、その子どもの中には、オスネコもいるわけです。すると、オスネコは、自分が大人になったときにオスとしてどう振る舞うべきかということが、そばにいるのは母親しかいませんから、わからない。そこでオスネコの性行動をどうするか、メスに対して、どういうものをメスと思うか、そのメスにどう迫るか、どう口説くか、というふうなことは、全部学習をしないでわかるようにできているらしいんです。 ところが、人間の場合には、親が育ててくれるし、そのときには両親が普通いるものですし、しかも、人間は、どうもたくさんの人間が……。要するに、アフリカにいたころには相当いっぱい、100人、200人と集団になっていて、集団の力でもって、ライオンとかああいう怖いものに何とか勝って、今まで生き延びてきたんだと思います。とにかくたくさん、100人、200人で生きるという、どうもそういう動物らしい。そうすると、子どもが育っていく間には、親以外にもいろんな他人が、いっぱいおじさん、おばさんがいるんです。そこからいろんなことをずーっと取っていく。教わるというよりも、取っていく、そういう動物らしい。 そうすると、その状況が今あるかというと、今はあんまりなくて、今はもっとプライバシーが大事ですから、団地の中に一家で入ってしまっていて、そして、男の大人は父親1人、女の大人は母親1人、いずれも1人ずつじゃないと困るんです。父親が2人いたりすると困るんです。だから、やっぱり1人ずつになるんです。だけど、この1人というのは、本来100人いるうちの1人ですから、いい意味でも、悪い意味でも、絶対中心値からずれています。母親も同じ意味でずれています。ずれた男1人とずれた女1人から、人間の大人というものがどんなものか、全部を学ぶことはたぶんできない。だから、それで変なふうになってくるんです。そうすると、やっぱり変な人がいっぱい出てくる。 このごろ、テレビを見ていますと、毎朝毎朝、何か変な事件が起こっています。ああいうのは、やっぱり何かそこらへんのところで、具体化のもとのところが、つまり、遺伝的プログラムがどんなものであるかということがよくわかっていないものだから、たぶんこれでいいんだろうと教育学者が思ったので、あるいは、社会の人が思ったので、それをつくってしまったというふうにやってきた。一夫多妻の文化もありますけれども、キリスト教なんかですと、一夫一妻なんていうのは、キリスト教になって初めてできたすぐれたシステムだそうです。そう思っている人もいるわけです。 だけど、それは、僕は動物学的に言って、人間はどういう動物かということを考えたときに、そういうものかなという疑問があるんです。そのへんの疑問がいろいろあるんで、そのへんもわからないんじゃないか。そうしないと、具体化の仕方がやっぱりわからないんじゃないかという気がします。それはとっても大事なことだと思います。 |
| 加藤: | 母親だけで育たないということを、日髙先生が、打ち合わせに行ったときにおっしゃっていたのが、人間は母親だけでは育たないと。 |
| 日髙: | ネコは、しかし、母親ですよ。父親がそこにいると、子どもがたいてい食い殺されてしまいます。 |
| 加藤: | 私がさっきから一生懸命言いたいのは、そういう要因は何なのかということです。個人差を超えたレベルで。 |
| 宮川: | ヒトは、たぶん遺伝的にすごく個人差があるんだと思います。しかし、ヒトの遺伝的プログラムの中には、たくさんある個人差をうまく吸収して、ちゃんとしたヒトに育てていくというようなプログラム、集団で育てることによって、それがちゃんとしたヒトになるというプログラムが実はあったと。 |
| 日髙: | と思いますね。 |
| 宮川: | 実はあったんだけれども、今、日髙さんがおっしゃったように、ずれた父親が、ずれた母親が1人1人、そして、ずれた子どもが1人出ています。そうすると、ずれた子どもがまたずれた父親になり、ということで、それがどんどんずれたヒトを生んでいく。ということで、本来は、たぶんヒトの遺伝的プログラムの中には、それを吸収するようなうまいプログラムができていたはずなんです。けれども、今は、現代社会では、そこがちょっとそういうことになってしまっているので、うまくヒトの遺伝的プログラムが具体化されてこないような状況になっているところで、そういうずれた人たちがいっぱい出てきていることがあると。 |
| 日髙: | そう思います。だから、遺伝的に……。 |
| 加藤: | だから、行動遺伝学の人なんかにやってほしいのは、個人差の前に、やっぱり本当に環境を変える実験をやって、それで、どう育って……。実験心理って、そういう分野ですよね。 |
| 宮川: | そういう実験はたくさんあると思います。 |
| 山縣: | だいたいこのあたりのところで、2部に入れなくなりそうな感じがするので。ただ、1つは、最後は、本当に、これからちょっと2部が終わってからになるかもしれませんけれども、ちょっと教育の話が出てきたと思うんですが、1つは、一言で、例えば、日髙さんなんかの言葉を借りて言うと、遺伝的プログラムというのはあるんだから、その遺伝的プログラムをちゃんと働かせるような環境を、そのつど、そのつど、きちんと用意していくということが、例えば、社会の役割だったり、教育の役割だったりというようなことになっていくのかなと。 そういうふうなシステムが、今、ちょっと崩れかけていて、何か違う方向に行っているかもしれないというようなことなのかなということは思います。このへんのところは、また後半のディスカッションとオープンにして、皆さん方からと思います。 ちょっとここで、皆さんにオープンにちょっとだけしたいと思うんですけれども、5分ぐらいしか時間がありませんので、質問とか、本当に20~30秒でお話ができる方で、何か質問を……。はい、どうぞ。 |
| フロアA: | 大変面白いお話をありがとうございました。日髙先生の今のご示唆というのは、本当に、僕は聞いていて、なるほどなと。私もちょっと霊長類のこととか、そして、人間の行動、もしくは遺伝、あるいは形態の進化というようことに興味を持っているんです。 いわゆる社会脳仮説とか、ああいうようなことでも、いわゆる学校のクラスなんか、だいたい人間の適正規模が50人だというのは、それ以下だろうということも言っています。実際、例えば、教育現場では、僕が持っている一般教養のクラスは、1クラス500人です。こんなのはまとまるわけがないというので、見ていると、親御さんが、要するに大学にお金を払い込んで、それで、頼むから大学だけは行ってくれというような感じで、親のために来てやっているという感じの人たちがやっぱりいるから、もうそれはどうにもならんわと。本人のモチベーションがないのは当然だろうなと。それは個人的な話ですが。 つまり、人間が遺伝的プログラムというのがある形で持ち合わせていると。さまざまな疾患とか等々ということによって、それがそれぞれある種の個人差を持つと。それはまさにそのとおりだと思います。 しかし、さっき、環境環境というふうにおっしゃたのは、やっぱり人間というのはほかの動物とは違いまして、非常に幼い形で生まれてきますよね。例えば、生まれてすぐ4つ足で立てたり、母親の乳を自分から吸うなんていうことはできなくて、基本的には、生まれたての子というのは、いわゆる世話をしてくれる人におんぶに抱っこと、そういうような形で生まれてくるわけです。  だから、基本的には、そこからあと、どう学習するかということから、いろんな、例えば、言葉を学び、行動の仕方を学び、あるいは、社会の習慣を学びと、そういうふうな形をとっていくという。それは、もちろんチンパンジーにもそういう面がありますけれども、人間の場合は特にそうですよね。 だから、やはり思うのは、そこで遺伝的プログラムと、もう1つ対になるのは、それを具体化する際の、いわば学習プログラムというものの適正化ということであろうかというふうに思う次第です。 それと、すみません、これは後で個人的に質問しますが、遺伝的プログラムの定義について、宮川先生に後で質問にまいりますので、よろしくお願いします。 |
|---|---|
| 宮川: | わかりました。 |
| 山縣: | 教育的プログラムといったところが必要ではないかというコメントでよろしいでしょうか。はい、何か。 |
| フロアA: | 僕は経験的レベルで話をしているのに過ぎませんので、そのことを、動物行動学および遺伝を学んでいらっしゃる方からコメントをいただきたいと、そういうわけです。 |
| 山縣: | はい、ありがとうございます。 では、前半のところは、こういうところで、後半、少し、今の発言にもあったと思うんですが、じゃ、本当に社会の中でこういった研究というのがどういうふうに、これは決してヒトの病気のことだけではないと思いますし、上のパネルにも、基礎的な研究だとか、それから、環境問題や食品の問題もすべてこういったゲノム研究というのが元にあったりして、生命そのものを解き明かしていくということの1つの手段になっているわけです。そのあたりのゲノム研究が社会とどういうふうにかかわっていくのか。それから、社会とのコミュニケーションとか、そういうあたりのところで、元村さん、加藤さんからお話をいただきたいと思います。 元村さんは、先ほどご紹介を少ししましたが、毎日新聞社で科学環境部の記者ということで、もちろんゲノムだけではなくて、たくさんの科学の分野のことについて、お仕事をされているということで、今日はゲノムのことでお願いいたします。 |
| 元村: | 科学環境部というのは、科学技術、それから環境問題を取材するところです。 日髙さんのお話ですごく気になったのですが、イヌ3匹とネコ3匹が生まれたという話。たぶん専門家からすれば、「なんちゅうばかなことを新聞記者は聞くのか」と思っているかもしれないんですけれども、ばかばかしいことも取材をするというのが記者の建前ですので、どうぞご勘弁いただきたいと思います。  最近、「ゲノム」という言葉を使った記事がどれぐらいあるかと思って、今年1月1日以来の記事を「ゲノム」というキーワードで検索したら、60本ぐらい出てきました。つまり、1週間に1回以上は「ゲノム」という言葉が載る記事が出ているということです。 スライドにはわりと最近のものを出しました。例えば、セイヨウミツバチのゲノムが解読されて、それをいろいろ調べると、匂いの受容体は発達しているけれども、味覚のほうは発達していないとか、コウモリはウマとかイヌに近いとか、ゲノムがわかることによって、いろいろ面白い発見がありますよ、という記事はわりと大きく載ります。それはやっぱり私たちが、今までの常識にてらして「へえーっ」と、ちょっとびっくりさせられるという体験、科学的な知識で説明される楽しさがあるからだと思うんです。「ゲノム」という言葉によって、何となくもやもやとしていた疑問がすっきりと説明されるというような、そんな期待があって、編集者の扱いも良くなるというようなことがあります。 ただ、一方で、扱いに迷うような記事もときどきあるんです。最近ですと、ニパウイルスという怖いウイルスがあります。オオコウモリからヒトに稀に感染すると、致死率が50%という、風土病に近いウイルスなんですけれども、そのニパウイルスを遺伝子を使って人工的に作ったというニュースがありました。 それは、逆にいうとワクチンの開発に役立つということで、前向きなお話ともとれるんですけれども、考えてみると「えっ、つまり、殺人ウイルスを兵器として使えるということだよね」とも考えることができるんです。マスコミとしては、どういう色づけをして、どれぐらいの大きさで伝えるべきかということを常に迷います。 平和なネタは、広く伝えたいと思うんですけれども、やっぱり表裏あって、怖い面、不安な面ということを、どうやったら正確に伝えられるだろうということに心を砕きます。 また「遺伝子診断ビジネスは危ない」という記事を、例えば載せますね。そうすると、読者は「危ない」というところに反応する人と、「へえー、こういうビジネスがあるんだ」というふうに反応する人と両方います。ニュートラルな記事というのはなかなかやっぱり難しくて、私たちが書いたあと、どういうふうに伝わっているかということまでは、責任が持てないなというのが悩ましいところです。だから、逆にいうと、ゲノムがわかったことによる恩恵ばっかりが伝わるのか、影の面ばっかりが伝わるのか、わからないことのほうが多いということが伝わっていないんじゃないかなとか、いろんなことを考えます。 最近、研究者も情報発信にすごく力を入れていらっしゃいますけれども、2004年の内閣府の世論調査ですと、「科学技術について知る機会はあんまりない」と言ってる国民が6割、7割近くいるんです。これだけ情報が発信されているにもかかわらず届いていないという状況がある。ただでさえ情報がたくさんある中で、小難しいゲノムの話がちゃんと届くという保証はなくて、そこがこれからの課題かなという気がしています。 これは、内閣府の同じ世論調査から抜き出してきたんですけれども、「科学の発展で心配になること。不安に思うこと」というのを、複数回答で一般成人男女に選んでもらった、多い順に並べたものです。8項目中3項目が、私から見ると、遺伝子やDNA、いわゆる生命科学分野に関する不安だと思います。つまり、遺伝子組み換えと聞いたときに、専門家の人は遺伝子組み換え技術でしかできなかったたくさんのいいことを知っていますが、あんまり知らない人は、遺伝子組み換え=怖い、遺伝子組み換え=食べたくない、うさん臭い、怪しいというふうに受け取りがちなところがあって、それが不安につながっていると思うんです。知っていたら不安に思わないのに、進歩がすごく早いためについていけない、だから不安に感じるというのが実際のところなのかもしれません。 もう1つ、私が外から見ていて心配だなと思うことは、生命科学でも、先端研究をする人たちの倫理観です。これは、1999年と2003年の2回、ほぼ同じ調査をした結果を比べているものなんです。2003年が一番最近のものなので、そちらを見ていただきたいのですが、「倫理問題への配慮」というのは、かなりの割合で意識している人が増えていますね。「常に意識」というのが、前は51%ぐらいだったのが7割に増えています。1999年は「無回答」というのがすごく多いんですけれども、それも減っていますし、意識するようになったことがこれで伺えます。 さらに突っ込んで、「あなたの研究で倫理問題がある可能性がわかった場合、どうしますか」というふうに聞いています。2003年時点の調査結果です。「すぐにやめる」というのが16%で、「可能性を公表する」人が26%、多いのは「マイナス面も研究する」という答えです。私は、これは許容できると思っています。つまり、マイナス面まで研究して、それをきちんと公開していくということそのものが、私は科学が社会に届く、あるいは、科学がいい面も悪い面も含めて社会に受け入れられることにつながると思っていますから。 しかし、若い人にあんまり当事者意識がないというデータもあります。「研究成果が予期せぬ悪影響を与えたときに責任を負うべきかどうか」ということについて尋ねた質問なんですが、「予測の範囲外でも責任を負うべきだ」と言っている人は、シニアほど高いんです。これは、マネージャークラスの人が高齢者に多いからということもありますが、「責任を負う必要がない」と言っている、35歳未満の若手が4割近くいる。これは、どういうつもりで答えたのかが気になります。 いずれ彼らはPI(研究代表者)として、中にはPIになっている人もいるんでしょうけれども、4割はちょっと多いかなという気がします。これから、予測できない悪影響というのはますます増えてくると私は感じていますので、詳しく知りたいなと思いました。 最後に、DNAについて、シドニー・ブレンナー(Sydney Brenner)さんがとっても面白いことを言っていたので紹介します。「DNAって何ですか」、「DNAがどういう時代を拓くと思いますか」という質問に対して、彼はこんなふうに答えていたんです。「Don't know anything.」、文章の頭文字を並べるとDNAになります。「何もわからない」と。 本当にわからないことがいっぱいあるんだ、これからわかっていくんだよということを、マスコミもそうですけれども、もう少し伝えていく必要があるかなと思うんです。この遺伝子がわかったから、あなたは絶対に太るとか、あなたは絶対にガンになるという、1対1のものじゃないんだということが、あんまり社会に伝わっていないんじゃないかなと思うんです。そこはとってもややこしい作業ですけれども、ていねいに説明をしてわかってもらう努力が必要じゃないかと思っています。以上です。 |
| 山縣: | はい、どうもありがとうございます。 続いて、じゃ、加藤さんから。加藤さんは、先ほどお話ししましたように、もともとは分子生物学者といってよろしいのでしょうか。そういう言い方は良くない? |
| 加藤: | 説明し始めるとややこしいので。 |
| 山縣: | 僕はその前をよく知らないので、要するに、こういう科学コミュニケーションというか、そこの、特にゲノムの分野でも日本を代表する研究者であるわけで、その加藤さんに、次にお話をしていただきたいと思います。 |
| 加藤: |  今、元村さんのお話を聞いていて、ちょうど受けることになるかなと思いました。それで、できるだけ短くしゃべろうと思うんですけど、1つは、ちょっと暗くてすみませんが、スライドで、ゲノムというのは、今日はあまりちゃんと出てこなかったので、本当にここに書いてあることだけ。右下に、1つの生物をつくり働かせるに必要な1セットの情報がゲノムなんです。それで、その中に遺伝子があって、それで、全体として働いて1つの生物ができる。例えば、左上にあるような、人間ができるわけですけれども、1つ確認したいのは、すべての生物がゲノムを持っているということで、ちょっと写真をと思って出したんですけれども、アゲハチョウのゲノムがあります。 左下にあるのは、私が自分で富山県の砺波市のチューリップ・フェアに行ってきて、珍しい八重咲きのチューリップの写真を撮りました。普通のチューリップと違って、何か非常に奇妙な感じなんですが、じゃ、これがどうできるかというのも、基本的にはゲノムの違いということで説明ができるんだと。 そういうことで、ゲノム研究というのは、皆さんは2003年にヒトゲノムの解読が終了したというので、よくご存じなのかもしれないですけれども、実はそれ以来、いろんなことが起こっていて、今日は時間の関係で、これをちゃんと説明しないんですけれども、要するにという感じで言いますが、上のほうにあるのは、人間のゲノムの研究が、今、多様性の研究、まさに宮川さんに話をしていただいたような個人の差、マウスの個人の差、人間の個人の差を調べようというようなことで、実際に何十万人、何万人の人のサンプルをもらうというような研究が始まっています。 もう1つは、下に書いたことですけれども、今、数字をちょっと見ていただいたらと思うんですが、400種以上の生物の解読はもう終了していて、進行中は1,000以上なんです。それで、その中には、本当にいろんなものがありまして、もうこっち、次を見せちゃいますけれども、ミツバチの解読が、つい1カ月前ぐらいに発表されたのですが、これなんか非常に面白いですね。ミツバチの典型的な社会性のプログラムが、ゲノムにどう書かれているのか。これは、私個人的に非常に興味があるんですけれども、それは本当にプログラムがかなりを決めているので、それを知りたい。 それも含めて、今、いわゆる医学だけではなくて、そういう生態学とか、行動学とか、それから、畜産、食品、農業、工業、本当にいろんなところに研究が広がっていっています。 そうしますと、さっき元村さんがおっしゃった話と非常に重なるんですけれども、コミュニケーションを考えるとき、そもそも、ゲノム研究って何やというのがなかなか語れないんです。つまり、研究そのものがダイナミックに変化しているし、中の広がりが大きいんです。 3つぐらいちょっとポイントを書いてきたのですが、1つは、ゲノムそのもののイメージがどんどん変化していて、ちょっと前には「設計図」という言葉をよく使われました。新聞にも「設計図」って、最近使いますか。 |
| 元村: | あんまり使わないです。 |
| 加藤: | ほら、使わないでしょう。ここに引用したのですが、日本のゲノム・プロジェクトのリーダーだった榊佳之さんが、2003年の完全解読終了にあたって、すみません、これは「朝日」です。「毎日」じゃなかったですが。「解読を始めたときは、もっとわかると思っていた。ゲノムが読めれば全部わかると思っていた。でも、生物はもっと複雑だった」ということをインタビューに答えられた。もちろん、解読したこと自体はすごく大事で、これからいろいろ進むよという話をした前提の上ですけれども、話をした。どっちかというと、料理のレシピとか、舞台の台本という言葉がだんだん使われるようになっています。 それから、2つ目は、これはさっきから議論していることですけれども、遺伝的要因と環境要因。これは1つ目の話と完全に重なっているんですが、よくこういう図が出てくるんです。これはあんまり詳しく説明しないですけれども、遺伝的要因が半分で、環境要因が半分でと、この組み合わせですよ、とかいうのが出てくるんですが、これは違うと私は思うんです。 つまり、何か、同じものが、あっちかこっちかという話になっているんだけど、たぶんそうじゃなくて、今日の話は、遺伝的プログラムがあって、それを環境要因が引き出すということなんだと思います。だから、それは、ここまでがこれで、ここまでがこれで、ではなくて、引き出すのが環境なので、つまり、次元の違う話ではないか。 ですから、ある研究者の人に「これはどうですか」と言われたことがあるんですが、「あぶり出しの絵とか文字はどうですか」と。見えないんです。紙の上に書いてあるわけです。見えないわけです。でも、書いてあるんです。そこに火が当たって、熱くなって、文字が出てくるんです。そういうものなのではないか。つまり、下から当たる火が環境なんだ。そのへんも変化してきていて、でも、じゃ、どう表現したらいいのかというのは、研究者はわかっていない。 それから、3つ目は、さっきも言ったことですけれども、研究対象が非常に広がっていて、それで、ゲノム研究って何なのとなってきているわけです。でも、やっぱりゲノムというのは、ある基本的なものとしてあるというふうに、はっきりわかることと、広がりがあるという、そういう両方がある。だから、それを社会とコミュニケーションするときに、いろんなことを考えないといけないんですが、これは単なる議論の材料として、私は3つぐらいの分野が大事なんじゃないかなということで、今は1と2しか見えていないですけれども、3つのことを言います。 1つは、どのような方法で、だれを対象に情報を伝えて議論したらいいのかということなんですが、1つは、もうさっきから出ているマスメディアです。利点がありまして、それはやっぱり一度に多数の人に情報を伝えることができる。ところが、課題は、やっぱり事件物、センセーショナルなもの、あるいは、倫理的な問題、どうしても表に出られない、危ないとかと。これは、元村さんに言わせれば、そうやからそう出しているんやというか、そういうことかもしれないけれども、はたしてそれ以外の継続的な研究活動、例えば、2階で、上で見ていだたくような、「ゲノム研究勢ぞろい」で見ていただくような、さまざまな研究です。それで、僕なんかに言わせると、やっぱり地道で継続的な研究、それはマスコミがどこまで伝えようとしているんだろうか。医療だって、オーダーメイド医療というのは出てるんだけど、でも、その裏にはものすごく地道な研究があるので、だから、応用的研究もまた違う形で伝えているんじゃないか。 それから、学校教育です。小学校、中学校、高校、いろんな段階で、いろんなことができるはずで、学校教育が変わると、それこそ、さっきからいろいろ出ている、国民全体の意識まで変わるはずで、それはどうしたらいいのか。やっぱり僕の立場は、生命科学、それから、ゲノム研究は、こんなにダイナミックに変化している。それが、やっぱり反映されていないんじゃないか。されていなくて当たり前かもしれない。 それで、右上を先に見てほしいんですけれども、特に、大量の人に均一に情報を与えられるマスの問題に関しては、わかっていないということは、やっぱりどうやって伝えたらいいのかというのは、ものすごく弱いと思います。学校教育だって、たぶんそうだと思います。 そこでといって、オチがこの「ゲノムひろば」なんですけど、私は個人的な興味から言っても、それから、そういう社会を見渡した、少しは客観的な分析から言っても、やっぱり研究者参加型のコミュニケーション活動が大事なのではないかと思っています。その利点はいくつもあるんですが、少しだけ言いますと、実際、コミュニケーションに参加する人が、今の研究を知ることだというんです。研究者から話を聞きます。そうすると、特に、わからないということが、案外うまく出てきます。それから、もうひとつはその逆です。フィードバック、さっき、若い研究者の倫理観がないと言われましたけれども、それは若い人はそういう質問に答えさせられていないんです。でも、ゲノム研究、こういうところに来たら、「ゲノムひろば」なんかに来たら、やっぱりときどきそういうのはぽーんと出てくるので、ああ、どうしようかという経験を、例えば、25歳のときにするなんていうことが起こると私は思っています。 さらに3つ目、研究活動そのものにも良い影響が与えられると思っていて、これは、今日はあまり深く話はしませんけれども、実は、研究者同士の交流とか、それから、研究を説明することによって、ここに書いてありますね、研究の目的とか、意義とかいうことをもういっぺん考え直す。説明しようと思うと、わかっていないと説明できない。「その研究は、何のためにやっているんですか」とかいって、突然言われたら困るというのがありまして、そんなことを考えて「ゲノムひろば」というのをやっているので、それで、ただし、効率が悪いというのがあります。書きました。なかなか大変なんですね。今回でも、言っても、何百万人を相手にお話しすることはできない。 でも、私が思うのは、実は、日本には、生命科学関係で、10万人以上の研究者がいるということがわかっていて、その10万人すべてが、ほんのちょっとずつ動けば、世の中は変わるんじゃないかということをよく思っています。でも、これについてどう思われるかは、ほかの皆さんに今日は聞いてみたいなと思って、とりあえずこういう方法があるのではないかということで、私の話は終わります。どうも。 |
| 山縣: | どうもありがとうございます。 さて、後半の、社会との接点ということで、まず、メディア側から、こういうものをどう伝えるかという、伝えるときのことと、それが本当に伝わっているのかという話と、それから、ちょっと怪しいぞということと、あと、もう1つは、若いとは言わないけれども、研究者が自分たちの研究に対してどう責任を持つかどうかということに関しては、少し何か考え方がどうなのかしらというようなことがあると思います。 それから、あと、加藤さんからは、ちょっと衝撃的だったのは、僕たちがよく使う、ヒトの病気は遺伝と環境でという、2つのあの平面的なモデルが、でも、あれって、確かにすごく問題があって、私は、もしも時間があればお話ししたいと思いますが、ああではなくて、もうちょっとさっきの遺伝的なプログラムの、日髙さんの話に非常にマッチしたような形の解釈だったように思います。 少し、社会とのコミュニケーション、科学者と社会とのコミュニケーション、そして、その間のトランスレーターになるのか、それを伝えていく役割となるのか、そのメディアのあり方というか、そのようなことを含めて、じゃ、4人の皆さんでお話をいただきたいと思います。口火を。 |
|---|---|
| 元村: | さっき、2階の展示を見たときに印象的だったのは、しゃべっている院生や若い人がすごく生き生きとしていたことです。やっぱり研究室の中では下っ端だったり、実験ばかりしていたりとか、そういう下働きの人たちが社会の表舞台に出てきて一般の人と触れ合うのはすごく意味があるんだなあというのが1つ。もう1つは、私が、ショウジョウバエの遺伝子を操作して目から足が生えている写真を見て、「えっ、怖ーい」って思わず言ったんです。そうしたら、説明してくれていた若い人が、「えっ、何が怖いんですか」って聞いてくれたんです。怖いか怖くないか、そのギャップのことを言いたいんじゃなくて、彼らが、私が市民としてそういう感想を持っていることを知ってくれたことがうれしかった。なので、とってもいいなと思いました。 |
| 山縣: | じゃ、答えて、一言どうぞ。 |
| 加藤: | 私たちは、双方向コミュニケーションの場ですと「ゲノムひろば」を宣伝して、ちょっとでもこういうコミュニケーションについて知っている人から批判されるんです。ちっとも双方向になっていないと言われてね。意見を聞いていない。議論をしていないじゃないですか。説明しているだけじゃないですか。でも、実は、今の話が、私は双方向コミュニケーションだと思うんです。ぱっと何か言われた。それを聞いた。顔色が変わったみたいな、それは双方向コミュニケーションです。 |
| 元村: | でも、私みたいに厚かましい人じゃないと、研究者の前で「ああ、怖い」とか言わないんじゃないですかね。 |
| 加藤: | いや、一生懸命説明したのに、何か下を向いてしまわれたというのも、双方向コミュニケーションなんです。 |
| 元村: | 非言語コミュニケーションですね。 |
| 宮川: | そのためには、口で言えない人は、お願いゲノムに書いてもらうというのは1つの手かもしれない。いろんな意見の出し方で。 |
| 加藤: | 山縣先生の展示のところには、ツリーが置いてあるんです。モミの木の「お願いゲノム」と。まあそれは置いておいて、いかがでしょう、社会との、例えば、宮川さんなんかのところというのは、よくある……。 |
| 宮川: | どうやったら科学の現状を一般の方々にうまく情報を伝えていけるかどうかということなんですけれども、僕はアメリカに住んでいたんですが、アメリカですと、テレビでけっこう科学番組をやっているんです。アニメなんかで、『マジック・スクール・バス』、これは毎日やって、うちの子どもなんかは毎日見ていましたけれども、これは理科、科学のアニメです。それが、かなりエンターテイメントとして面白くできているんです。『マジック・スクール・バス』というのは、スクール、クラスがあって、先生がいて、子どもたちがいますけれども、毎回スクール・バスに乗っていろんな科学の場に探検に行くわけです。昔の恐竜の時代に行ったり、バスがぴゅーっと小っちゃくなって、人体の中に入っていって、細胞の中を見てみたり、そういうことをやるわけです。 それを毎日見ているんです。それは、べつに科学を学ぼうとして見ているんじゃなくて、面白いから見ているんです。そういう番組は面白くつくってある。そういうところに、ナショナル・サイエンス・ファウンデーションとか、そういう実際の科学のファンディングのお金が出て、やっているんです。そういうのはかなり強力で、やっぱり面白い。子どもが自分から面白がって見るという、相当強力なんです。 そういうのを何とかできないか。あるいは、例えば、ドラマでもいいですね。ドラマのちょっとしたところに、本筋じゃなくていいです。本筋は科学者のこういう格好いい人と、この人がちょっとくっついたり離れたりとか、そういうのが本筋でいいんですけど、ちょっとおまけで科学の内容が入っていて、自然に知識が入ってくるようなのだと、やっぱり見るんじゃないですかね。そういうのがあったりする。 |
| 加藤: | 生命科学はどれぐらい入っているでしょうかね。 |
| 宮川: | 生命科学……。 |
| 元村: | 『不機嫌なジーン』だ。テレビドラマがありましたよね。 |
| 宮川: | そのへんはちょっと見たかったですけど。 |
| 元村: | TBSでネプチューンがやっている理科の番組は、ご覧になったことはありますか。10月から始まったんですけど、面白いです。『ネプ理科』でしたっけ、科学番組があります。 |
| 加藤: | もしかして、関東でしかやってへんのかな。 |
| 元村: | それはNHK教育テレビとはまた違った感じで、面白いから見るんですけど、へえーっという場面も5~6カ所出てくるんです。 |
| 加藤: | それはものすごい可能性があると思いますが、ただし、やっぱりどうしてもミクロのサイエンスは、バランス的に少なくなる可能性がある。アッテンボロー(Attenborough)の有名な自然シリーズがあるんですけれども、僕はイギリスに行ったことがあるんで、そのほうがよく知っています。それで、植物のシリーズをものすごくていねいにやったときに、私のまわりのサイエンティストたちが、なぜあそこで花を咲かせる遺伝子の話をしなかったんだという。それはなぜか聞いたところでは、やっぱりBBSのプロデューサーが、これは難しすぎるから却下したと。 |
| 元村: | 難しすぎるからというのは、ある意味、おせっかいなんですよね。ただ、テレビの人がよく言うんだけど、「これは持たない」と。持たないってつまり、長々と説明していたらチャンネルを変えられてしまうから、はしょったり映像で見られるものだけにするという雰囲気があるんです。 |
| 宮川: | メジャーなチャンネルだと、たぶんそういう問題が生じてくると思うんですけど、そういうところでは、そのネプチューンの。 |
| 加藤: | それを言うんやったら、日本でもやっているんです。CSで、『サイエンス・チャンネル(Science Channel)』って知っていますか。 |
| 元村: | マイナーですね。 |
| 宮川: | 『ナショナル・ジオグラフィック(National Geographic)』とか、『ディスカバリー・チャンネル(Discovery Channel)』は日本でもやるようになりました。あれは、たぶん非常に良くて、けっこう見ているんですけれども、ああいうところだと、見たい人が見たいときに見て、そんなに視聴率を気にしないという状況でできることなので。でも、ああいうのはやっぱり、どこか外国でつくられたものをやっているんです。日本でそういうものが少しでもいいからつくれないかなということで。 |
| 山縣: | 例えば日髙さんにしても、ご自分の研究がいろいろ社会にメディアを通して報道されると思うんです。そういうときに、何かこう、あれっとか思ったり、いやいや、こういう伝え方もあったのか、というふうに思われたようなことってありますでしょうか。 |
| 日髙: | いや、そういうときに、いつも苦労するんだけど、僕は物を非常に素人的に発想するんだと思うんですけれども、非常に変な疑問でも、「なぜ?」とか、そういうふうな具合のことがあって、非常に普通の人が感じるような疑問であると、その先はけっこう難しいところまでついていけるんだと思うんです。初めのところの疑問がすごくわからなくて、えらい学問的な疑問だと、あとはたぶん人はついてこられない。 要するに、僕自身の感覚というか、思い出してみると、子どものころに校長先生にいじめられたものですから、学校へ行くのが嫌になっちゃって、今でいうと不登校児になっていたんです。そのときに、学校へ行くのをサボって、近くの原っぱへ行って、いろいろ木が生えているので、小っちゃな木、その小枝を見ていると、イモムシの小っちゃいのがちょこちょこ、ちょこちょこ歩いている。何か、一生懸命歩いているんです。つい、そのときに、聞きたくなるんです。「おまえ、どこへ行くつもり?」って聞きたくなる。「何を探してるの?」。もちろん返事してくれませんから、見ているほかはないんです。見ていると、ずっと歩いていって、どこか脇にちょっと木の芽が出て葉っぱがついている。そこへ行って、急にむしゃむしゃむしゃと食べ始めるわけです。それを食べているのを見ていて、「ああ、これが欲しかったの」というんで、何かすごくうれしかったという記憶があるんです。 何かそういうような発想というのは、どういう場合でもあり得るんじゃないかと。それは、今、こういう研究所にいると、専門家がいっぱいいるわけです。その専門家の中には、哲学の専門まで入っているんですが、やっぱりそういう人々が、大変難しい発想をするんです。もう少し素直な発想をしてくれないかなと、つい思うんですよ。あんまり難しい発想をされると、その先、こちらもついていけなくなっちゃう。何かそのへんのところは非常に大事で、それは、どうやったら教えられるだろうかといって、一生懸命苦労している人がいます。でも、そういうものなのかなあという気がしてしょうがないんです。 |
| 山縣: | どうすれば、「なぜ」と思えるのかという教育ですね。それはむしろ人に備わっている、まさにそれが遺伝的プログラムであるんだけど、それが見えないようにしている環境のほうが問題なのかもしれないですよね。 |
| 日髙: | だと思いますね。 |
| 元村: | 生物教育の学会に出て、学校の報告を聞いて「へえ」と思ったのは、生物の授業は受験校ほど味気なくて、受験とあまり関係がない、大学進学率が4割を切るような高校のほうが、先生がのびのびと授業をやっているということなんです。「今日は天気がいいから河原に行こう」なんて、子どもたち、もう高校生ですけれども、河原に行って写生をする。そのうちに虫を追いかける子が出てきたり、観察に熱中し始める。そういう豊かな教育というのがどこでもできればいいのだけれど、将来研究者になったりする人たちが比較的多い受験校の方が詰め込み教育をやっている。 すごい矛盾だと思います。科学者って、自分でなぞなぞをつくって自分で解ける人でしょう。それができづらい環境があると思います。 |
| 宮川: | その点は非常に重要なポイントだと思うんですけれども、今のって、僕のときもそうなんですが、日本の理科の教育というのは、わかっていることだけを教えるんです。それで、「なぜ」という素朴な疑問というのは絶対あるはずなんですけれども、「なぜ」というのに答えていくという形ではない。それから、現在の科学の先端で、どこまではわかっているけれども、どこから先はまったくわかっていないと、謎であると。その謎を解こうとしている先端もあるとか、そういう話は全然しないんです。 それがありまして、僕は、こういうお話をさせていただきましたけれども、文学部出身なんです。文学部なんです。文学部に入って、今、こういうことをやっているんですが、それはどういうことかといいますと、僕はもう「なぜなぜ」派だったんです。「なぜなぜ」派でありまして、理科とかもとっても好きだったんですけれども、物理の教科書、それから、生物の教科書を見たときに、もうほとんど何かわかっているんじゃないかという誤解を持っちゃったんです。そのときはそう思った。もうほとんど、物理は、ああ、そうか、もうこんなにニュートンのあれでわかっているのか。それから、陽子のあれでもうわかっているのかと。生物も、こうなって、こうなって、こうなってとわかっていたら、もうあんまりやることがなくて面白くないんじゃないかなと思っちゃったんです。 それで、しょうがないから、社会のこととか、心のこというのは、まだ研究で、どこの教科書にもそんなのは全然出ていませんから、そういうところだったらフロンティアがあって、「なぜなぜ」ということがいけるんじゃないかなと思って文学部へ行っちゃったんです。そういう誤解を招く、誤解であると言っちゃったんですけれども、誤解を招くような教育になっているというものがどうなのかと。 |
| 山縣: | だから、ゲノムの研究者って、例えば、こうしてやっぱり多いと思うんです。なぜと思うからそうやっていく。例えば、そういうことを、こういう「ゲノムひろば」だとか、ほかのところに伝えることはとっても大切だと思います。例えば、メディアが、研究の成果はこうだったんだけど、それはなぜそうだったのかと、例えば伝えることができるのかとか、伝えようとされているのかというあたりはどうなんですか。 |
| 元村: | 私が5年ほど続けている「理系白書」というのは、そこを伝えたくて始めたんです。なんで今までの科学ニュースは成果ばっかり伝えてきたのか。「こういうことがわかりました」「こういうものを発見しました」という成果はもちろんニュースなんですけど、その裏に人がいるということが全然伝わっていないということを、私は読者としてずっと感じていたというか、読者だったときは考えもしなかった。科学環境部に来て、研究者を取材するようになって、ああ、研究の裏には研究者がいたんだというシンプルな事実に気がついたんです。 私はそれまで読者でもあったわけで、知ったときに「ああ、読者にはそれは伝わっていないな」と思ったから始めたんです。伝えようと思えば伝えられます。 |
| 加藤: | でも、ちょっと確認させてください。研究者が伝わるということと、研究に裏というか、長い歴史があったり、わかっていないことがあるということを伝えるのとは違うと思います。 |
|---|---|
| 元村: | ただ、研究者の人たちの生き方を伝えることで、わかっていないことを追いかけている人種だということは伝わるんじゃないですか。 |
| 宮川: | どういうモチベーションでやっているのか。 |
| 元村: | うん。 |
| 宮川: | どうしてそんなことを研究しているかというところも……。 |
| 加藤: | ちょっと、元村さん、さっき振られたので、自分としては受け止める責任があると思うんです。例えば、ニパウイルスをつくられたというような話が出たときに、あれは何が足りないのかなというか、書き方というのはあれでいいんでしょうか。 |
| 元村: | それで、迷った結果、すごくシンプルな記事になりました。同僚が書いたんですけれども、いろいろ考えた結果、「ニパウイルスを遺伝子からつくり出すことにだれだれさんが成功した」というところで終わっています。つまり、主語と述語だけで終わっているということです。で、コンパクトに、まあ目立たないようにと言うとちょっと語弊がありますけれども、あっさりとした感じで載せています。 でも、それを1面の頭に仕立てろと言われたら、いろんなコメントを取って、生物兵器の現状とかを一緒に合わせて、だーんと、こんなものが日本の感染研でつくられていたと展開することもできるんですけど。 |
| 加藤: | 何か、でも、そういうのが、表と裏みたいな絵になりますよね。研究者的には、もうちょっと連続的にいろんな見方があるとか、影がないわけじゃないんだけど単純じゃない。そのへんが伝えられたら……。 |
| 元村: | あそこにギャップがあるんですかね。 |
| 山縣: | あともう1つ。たぶん市民の立場からすれば、濃淡のつかない情報みたいなものを欲しているところもあるんじゃないかとか、今のことを普通に淡々と知りたいとか、例えば、新聞に出ることしか知らないのでは困るし、そこで、いいよ、いいよと言われているものだけでも、ほんまかいな、という気にはなってくるし。そういうのを、ニュートラルって何かよくわからないんですが、今みたいに、「だれだれが何々を発見しました」というような、そういうふうな情報がずーっとこうあるようなことって、まず何か、情報を提供する側も、それから、それを今欲しいと思っている人はけっこういるんじゃないか。逆に、でも、それをもってどうするかって……。 |
| 加藤: | それで思い出したんですけれども、これ、ちょっとこういう言い方をすると、自分たちの宣伝になるんですけど。 |
| 山縣: | ええ、宣伝しましょう。 |
| 加藤: | これをつくったのは、実は私の研究室で、「一家に1枚周期表」の第2段で、全国で10万枚配ったんですけれども、ヒトゲノムマップ、これをつくって出したときに、全貌が載っているんですが、こういうのを今まで見たことがなかったと。シークエンスされたという言葉としての表現は知っている。それから、個別の遺伝子の話は何か載っている。毎日毎日載っている。全体を見たのは初めてと言われたんです。ちょっとそのへんに通じるものがあるような気がします。 |
| 元村: | うん、そうですね。確かに、ずーっとACGTが並んでいるやつは、『ネイチャー』の付録とかでもらいましたけれども、機能とか意味まで載せたというのはあまりないですね。10万枚、全部さばけましたか。 |
| 加藤: | 4万枚が全国の小・中・高に1枚ずつ行きまして、かなりの学校では、理科室に貼ってあって、あと、5万枚ぐらい、博物館、科学館に出て、それで、さらに、今、有料配布しています。 |
| 元村: | 周期表は35万枚だったかな。 |
| 加藤: | ええ、なかなか勝てないです。 |
| 元村: | がんばってください。 |
| 山縣: | さて、そろそろ時間もないので、ただ、今日は、本当にここの談議を聞いていただくというのを最初のお話は主にしたんですが、それでも、フロアから1つ2つ、何かあればと思うんですが、じゃ、そちらの方。 |
| フロアB: | 私もまあこんな年、もう71歳なんですけど、25歳のときにちょうどクリックさんと(ワトソンさんの)2人が2重螺旋を発表されて、非常に驚いた自分なんです。今日、こういった「ゲノムひろば」に寄せていただいて感じたのは、遺伝子、私らの頭でいきますと、1遺伝子1タンパク質と、これしか知らなかった。ところが、1遺伝子はけっこう複数のタンパク質でつくるんだということとか、あるいは、イントロン、エクソンではなくて、イントロンにもけっこう働きのある配列があるとか、あるいは、ハプロタイプの遺伝子ですか、あれの中のタグスニップですか、こういったものも初めて私は聞いたんです。  大変いろいろ勉強させていただいたんですが、まだ、今、聞いておりますと、さっき記者の方がおっしゃっていたように、DNAとは何やと言ったら、Don't know anything.つまり、まだ何もわかっていない、そういう段階ではないかと思うんです。そうした場合に、ちょっと話を聞いておりますと、DNAを調べるということに関して、日本では非常に封鎖的というんですか、いろいろプライバシー問題等がありまして、個人情報保護法の壁があって、ちょっとそれが先行しすぎているんじゃないかなと、こういうことを感じるんです。まだ、今現在では、おそらく、私の考える限りでは、ことゲノムに関しては、トライアル・アンド・エラーという考え方から行きましたら、まだ意見なしで、無礼講で話し合える段階の時期じゃないかなと。ちょっとこれは、言うことがわかっていただけるかどうかわからないんですけれども、そういう時期じゃないかなと思うんです。 そういう意味で、ある一定期間は、どういう発言をしても、あるいは、記者の方だったら、どういう報道をしても、無礼講で行こうと、こういう期間があってもいいんじゃないかと思うんです。 先ほどちょっとどなたかがおっしゃっていました、アイスランドではDNAを全国民から採っていると、こういう話もちょっと聞きました。あそこは島国ですし、日本と非常に共通点を持っています。そうしますと、遺伝子距離もみんなそれぞれ近いですので、病気遺伝子とか、そういったものがわりあいと早く抽出できるんじゃないかと思うんです。でも、日本が個人情報、個人情報といって、やれプライバシーだといって、それで足踏みをしている間に、向こうはもう本当に、次々といろんな因子を見つけていって、どんどんどんどんその差が開いていくんじゃないかと思うんです。こういうあたりをちょっとまたお考えいただけたらいいということです。 それともう1点だけ。今現在、同意書をもらってもDNAの資料を採取できない種類の業種というんですか、業種じゃなしに分野というんですか、どういう分野があるんでしょうか。それをちょっと教えていただきたいと思います。 |
| 山縣: | ちょっと倫理の問題なんですけれども、もう時間なのでありますが、今、ご存じのように、国の倫理指針というのがいくつか出ていまして、研究の倫理指針や、それから検査に対する倫理指針というのもありまして、そういう中で今規定されているわけです。基本はいくつかあると思うんです。1つは、やはり遺伝子の、というのは、やっぱり個人のプライバシーの問題があるので、とにかくその人の同意、自発的な参加というのが一番大切であるという点と、そういったものをどういうふうにきちんと個人情報を安全に取り扱うシステム、環境をちゃんとつくっておくかというようなことです。 あと、もう1つは、今あった、結果みたいなものをどういうふうに公表していくかというのはすごく問題だというふうに思うんです。本当に、例えば、1個の遺伝子がわかったからと、それは本当にそうかどうかというのはわからなかったりするわけです。でも、やっぱり出ると、みんなそうかなと思ってしまうところがあって、そういう結果の発表に対して、そういうところに、今お話しになったような、自由にディスカッションして、この情報ってどういう意味があるのかといったようなリテラシーも持ちながら、そういうものを理解できる、そういう環境とかというものが必要だというご指摘なのかなというふうに思いました。細かいことは、もしあれでしたら、またフロアでお願いします。 ちょっと時間がないので、誠に申し訳ありません。後ろの方、1つ、本当に大変短い時間しかないんですが、よろしいですか。はい、白い方。 |
| フロアC: | 本当は、1部と2部、両方を通して1つずつ言いたいことがあったんですけど、ひとまず、今は2部が終わったところなんで、2部のほうだけなんですが、さっき、科学の発見がなされた成果は新聞に載るけど、その途中段階とかいうのは、やっぱり……。新聞とかテレビというのは、部数とか視聴率も多少は絡んでくることもあって、全部が全部、一般市民に伝わっていない部分がたくさんあると思うんです。 だけど、個人的には、まだこういう目的があって、こういう研究に取り組み始めたとか、そういう、まだ結果が出るかわからへんところとかも、知りたいという気持ちは強くて、やっぱりそこらへんは連携が足りていないというのはよく言われるんです。逆に、科学者の立場からしたら、研究の競争みたいなものも、海外ともやっぱりあると思うので、そこらへんが、今、逆に、なんで科学者はもっと公表しないのかというのが強く言われているほうだと思うんですけれども、どっちも問題を抱えていると思うんで、そこらへんの関連というのを、もうちょっと積極的に、全部が全部公開できないのもわかった上で、もっとアプローチの仕方があると思うんで、そこらへんをもっとお願いしたいと思います。 |
| 山縣: | ありがとうございます。今のことを少し踏まえてではないですが、本当に一言ずつ、15秒ぐらいになると思うんですが、例えば、研究者なり、それがどう社会に向かってとか、それだけではなくていいと思うんですが、今日のコメントでもいいので、本当に一言ずつ。じゃ、日髙さんから。 |
| 日髙: | いや、特には。 |
| 山縣: | よろしいですか。はい、宮川さん。 |
| 宮川: | ご指摘があったように、科学者はもっと情報を国民の皆様というか、どんどん出していくべきだと僕は思います。なぜかというと、われわれは研究しているんですけれども、その研究に使われているお金、研究費というのは、ほとんどすべて税金でやっています。ということは、皆様、働いていらっしゃる方は、ほとんどの皆さんは税金をお支払いになっていると思いますが、そのうちの何割かは……、何割もないですね、ごくわずかだと思いますが、一部が研究に来ているわけです。それで研究をやっているわけです。ということは、われわれはあんまり気にしていないので、そこのところをよく研究者はわかった上で、インターネットとかを通じて、ホームページとかを通じて情報を公開して、あと、インターネットにもちょっと方向性の部分を入れておくといいんではないかと思います。以上です。 |
| 元村: | 新聞から科学の情報を得ている人って、6割ぐらいいるんですけれども、それですべてとは全然思っていません。例えば、ここにいる方々は意識が高い人なので、私は心配していないんですよ。ここに足を運ばない人たちに、私たちはどういう情報をどう届けるかということを常に考えます。今日、たくさん宿題をもらいました。地道な取り組み、わからないこと、続いていること、これから始まることというのを、もう少し気をつけて取材をしていきたいと思います。 |
| 山縣: | ありがとうございます。加藤さん、どうぞ。 |
| 加藤: | 私は企画者側なので、どういう表現をしようかと思って、かなり、さっきぐるっと回っていたときに考えました。正直に言います。けっこうフラストレーションが溜まったななんて。なぜか。それは問題がものすごく大きいんです。遺伝と環境、それから、さっき元村さんがおっしゃいました、ジャーナリストの役割、それから、そういうウイルスのテロの問題とか、ものすごく大きな問題が今いっぱい出た。これは、やっぱりもっといろいろ語らないと、何か皆さんと話ができたという感じが全然していないなという感じがしています。 だから、何が言いたいかというと、たぶんさっき宮川さんがおっしゃった、インターネットも大事、メディアとの連携も大事なんだろう。それから、「ゲノムひろば」的なものも大事なんだろうという、いつものオチなんですが、ちょっと全然足りひんなあみたいな、どないしましょう、みたいな感じが。 |
| 山縣: | そうですけど、また持たないといけないですね。 |
| 加藤: | ええ。でも、それを前向きに、皆さん、また付き合ってくださいというのが、どちらに対しても、私の感想です。 |
| 山縣: |  ありがとうございます。今日、タイトルは「遺伝か、環境か」とかというところから始まったんですが、1つとしては、「遺伝か、環境か」ではなくて、「遺伝であって、環境であって」というような、遺伝的プログラムというものがあって、そこに適切な環境というのが必要だということです。そのためには、遺伝プログラムは何ぞやということをきちんと研究しなきゃいけないだろう。そこがわかっていないんじゃないかと。それを研究するのは、やっぱりゲノム研究じゃないのかと。そう考えると、やっぱりまだわかっていないことだらけで、1つ1つの遺伝子だけではないんだろうというところで、まだまだこれから、遺伝、ゲノムの研究というのは重要なものであり、そして、そういうところに目を当てて考えいかなきゃいけないということだったような気がします。 そういったようなことを、今、この研究というのは、さっき税金でということがありましたが、それ以外にも、やっぱり市民と一緒に、どういう形でそれを研究していき、情報をお互いにコミュニケーションしていくかということも、今フラストレーションという言葉もありましたけれども、やろうとすればするほど、ああ、こうではなくてというところがあるので、そのあたりのことも一緒に考えていきながら、このゲノム研究というのを考えていく必要があるのかなというのが、1つの、私が今日皆さんから得ることができたことだったと思います。 5分ほど時間は過ぎてしまいましたが、これで「ゲノム談議」を終わりにしたいと思います。今日は本当に、パネリストの皆さん、どうもありがとうございました。では、これで終了いたしたいと思います。(拍手) |
※ゲノム談議は、ゲノム研究の社会的・時代的意義について、ざっくばらんに議論することを目的に開催したものです。内容について、厳密な意味では科学的に正確でない部分や、表現が偏っている部分がある可能性がありますが、当日の議論をそのまま紹介しています。ご了承ください。